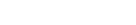思いをぶつけ合い、化学反応を生む 若手社員2人が現場目線で挑むDX
思いをぶつけ合い、化学反応を生む
若手社員2人が現場目線で挑むDX


デジタル化が急速に進む中、DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みは、あらゆる企業が直面する課題であり、大きな変革が迫られています。未来を見据え、新たなビジネスを生み出す、そんなDXの現場で奮闘する、同期社員2人の挑戦と思いをお届けします。
プロフィール

-
大橋祐太
2017年入社。アルコール化学品部(メタノールチーム)にて日本市場を担当。その後、19年7月に液体化学領域の物流効率化に取り組むケミくる(株)を立ち上げ、現在は事業責任者として事業開発を担当。(2020年9月取材当時)

-
加我一生
2017年入社。調査部(産業調査チーム)を経て、19年4月よりデジタル戦略部(企画チーム)にて、HERE Technologiesへの出資案件を推進。20年4月よりデジタル戦略部(事業投資推進チーム)にて、同社成長戦略の策定を担当。(2020年9月取材当時)
目次
課題起点で生まれた新規事業「ケミくる」

大橋くんは、2018年に旧化学品グループで開催されたビジネスコンテスト「Chemical x Tech 2018」で「ケミくる」の構想を起案し、事業化を実現したんですよね。
はい。液体化学品の効率配送を実現するソリューションとして、配車マッチングサービスを立ち上げました。メタノールの国内販売を担当する中で、ドライバー不足から配車手配が難しくなるという課題に直面し、これを解決したいと思ったことが構想のきっかけです。
入社して1年が過ぎた頃で業界知見は全くの素人でしたが、とにかく粗雑ながらも、自分の課題意識と考えをチームに発信し続けたところ、上司から「ビジネスコンテストで起案してみては」とアドバイスが。週1,2回、3カ月にわたり熱心に事業化プランの相談に乗ってくれていたことが大きな支えになりました。


個の力を組織の力に変える上で、上司やチームの方のサポートは大きいですよね。大橋くんのように、声を発すると後押ししてくれる環境は、実は三菱商事にはたくさんあるんじゃないかと思います。自分で考えた課題や気付き、こんなサービスをやってみたらどうかという声を、臆せずにまずは発してみる。それが、僕ら若い世代にとって極めて重要な気がしますね。
同感です。私も環境に恵まれ大変感謝しています。事業化に向けては、正直分からないことばかり。ビジネスコンテストから継続する形で、グループの新規事業開発支援やアドバイスを受け、顧客や運送会社、競合の他商社などへの徹底的なヒアリングを行いました。そこでは、皆が同じ悩みを抱えていることがわかっただけでなく、中には競合にもかかわらず「解決してくれるなら発注する」と強く共感してくれる方まで現れました。起案当初から、業界全体が心から解決を願う課題が確信できたことも大きな力になりました。

 ビジコンへの起案を後押ししてくれた上司と
ビジコンへの起案を後押ししてくれた上司と産業DXはトライ&エラー ~悪戦苦闘の日々

創業2期目の手応えはどうですか?
少しずつ前進しているものの、率直にお話しするとかなり苦戦しています。
「ケミくる」では当初、効率配送を実現するため、荷主の「納入時刻指定」に着目しました。液体化学品の配送車両は1日1回転の稼動が多く、調査するとオーダーの8割が午前指定、その半数以上が時刻指定だと判明しました。そこで、運送単価を抑えることで時刻指定のない荷主を募り、1日2回転を目指すことに。単価を抑えても稼働率が上がり、運送会社にとっても十分な収益増が見込める算段でした。しかし、景況感が下がり、当初のコンセプトと足元の課題のズレを軌道修正する必要が出てきたのです。


新規事業の難しいところですね。
はい。1日2回転するためには、荷主のオーダーが一定量必要ですが、この想定が甘かった。特に2019年秋以降の景気低迷で、配送需要が大幅に落ち込んだのです。配送効率の観点から、距離だけでなく「納入時刻指定」も価格要素にするムーブメントを作りたかったのですが、このルールメイキングは機能しなかった。そこで、納品タイミングに融通を利かせるコンセプトから、パートナーとなる運送会社車両が「空いていれば」車両提供を受ける形でマッチングを行う仕組みを目指すことにしました。


解決を目指す課題・目的はそのままに、事業推進の過程で見えてきたハードルを捉え、事業アプローチを大きく変えたわけですね。
はい。グループの事業開発支援組織と壁打ちを繰り返し行い、あるべき方向性を模索しました。荷主や運送会社に絶えずヒアリングを重ねた中で、「配送」だけでなく「受発注業務」にも大きな課題があることに気付き、まずはこの課題を解決するべく、事業の方向を転換することにしたのです。荷主、運送会社間のやりとりはFaxなどのアナログ手段が中心、配車は大手運送会社でも紙やExcelなどが使用されており、業務負荷がかかっていました。そこで、私たちが荷主と運送会社の受発注業務も事業範囲に取り込み、関連業務全体をデジタル化し、両者がクラウド上で効率的にコミュニケーションを行い、データを活用しながら、最適なオペレーションを選択できる、そんなビジネスモデルを目指そうと考えました。このサービス上で配車計画を立てれば空き車両が可視化され、「空いていれば」車両提供を受けるネットワークも実現でき、当初解決を狙った「配送」課題にアプローチできると考えたわけです。


新規事業では、外部環境がめまぐるしく変化する中で、走りながらキャッチアップし続ける力と、対応のためのアクションスピードが強く求められるという話を聞きます。大橋くんの取り組みは、まさに自ら変化を起こそうという気概を感じますね。
ありがとうございます。2020年8月から、配車のマッチングと受発注業務を両立するシステム開発に着手しています。要件定義が重要ですが、ありがたいことに、私の出身であるメタノールチームから、最初の顧客として全面的なサポートを得て進めています。高いプレゼンスを誇る既存事業と協業しながら、産業レベルでのDXに挑戦していきたいです。



「俺にとってのDX」「私が目指す事業経営」を語り合う

社内には顧客にもパートナーにもなり得る場があり、これを活かして新事業やサービスを創ることは、まさに三菱商事がやるべきことそのものですよね。既存事業の強みを活かした座組みも、産業DX(※)には不可欠だと感じます。一方で、DXという言葉は大変難しいと思いませんか?
※ 三菱商事が目指す、事業の効率化や生産性向上につながる機能をプラットフォーム化し、あらゆる産業に対して企業の壁を越えて提供することで産業全体の変革を促進するDXのこと。
人によってさまざまな解釈があり、目線合わせが重要ですよね。


最近、大橋くんとは「俺のDX」「私の事業経営」って話を良くしますよね。一人ひとりがもっと考えたら、もっとワクワクするんじゃないかと。取り組むべきDXやサービスを自分なりに考え、世代を超えて互いが思うDXをぶつけ合い、そのイメージを磨き込むことが重要だと思います。そういうムーブメントから、面白い化学反応が生まれるんじゃないかと最近すごく感じますね。
抽象的に思える概念を腹落ちさせるために、対話は重要ですよね。


僕自身も大変悩みながら解釈してきました。今、本質的に求められているのは、社会や顧客に高い価値を創出し続けるために、ビジネスモデルを変革すること。いかに価値あるサービスを提供し続けられるかです。テクノロジーは、課題解決力を次のステージに押し上げる1つの手段であり、カギだと考えています。業界を変えたいという思いと、作りたいサービスにテクノロジーをどのように伴走させるか。そして、いかに社会や産業のサステナビリティ、三価値同時実現(※)を達成するか。これを一丸となって考え実行することが三菱商事のDXだと思います。
※ 経済価値、社会価値、環境価値の三つを実現しながら持続的な成長を目指すとした三菱商事の経営方針。
産業レベルのデジタル変革 三菱商事の新たな「攻め筋」
加我くんは今、どんなことにチャレンジしていますか?


HERE・三菱商事・NTTの3社アライアンス(※)の全体戦略の策定とオペレーションの構築に取り組んでいます。複数の事業領域や地域にまたがるサービス開発を加速し、アジア市場における成長の実現や、HEREがこれまでメインで事業を展開してきた自動車領域から、自動車以外のさらに幅広い事業領域における成長の実現を加速していくことが、私の挑戦です。
三菱商事の強みはリアルの世界のオペレーションに入り込んでいることです。ここで得られる産業知見や課題認識、ネットワークをデジタルの世界につなぎ込む。そしてオペレーションをデジタル化し、場合によっては仕組みそのものを新たなものに作り変えてしまう。この動きを大きく加速する触媒が「位置情報」です。そして、モノやヒトの動き・属性を可視化して、産業の課題を解決するサービスの創出を後押しするための基盤が「HERE」のプラットフォームです。
※ 「HERE Technologies」は、カーナビ向けの位置情報サービスを提供し、世界最大規模の位置情報データベースを基盤にヒト・モノの移動に関する幅広いサービスを提供するリーディングカンパニー。
三菱商事は2020年、NTTと共同でHERE社に出資。社会課題の解決に向け、都市交通、位置情報サービスの3領域におけるさまざまな取り組みを進めています。
産業規模での変革を志す三菱商事にとって、そのような武器となるプラットフォームをポートフォリオに組み込んでいくことは、今後の大きな優位性になるのでは?


はい。しかもHEREはグローバルなプラットフォーマーなので、国内外の産業向けのサービスモデルを多極的に立ち上げ連携させることも視野に入れています。国や地域を越えて事業を展開できることもデジタルサービスの優位性であり、三菱商事の新しい攻め筋になると考えています。
加我くんは、HEREとの事業の中でどのような役割を果たしていますか?


デジタル戦略部と、社内横断的にDXに取り組む組織「DXタスクフォース」の仲間と協業して、HEREの経営陣や営業・開発担当、顧客候補となる幅広い外部企業と粘り強くコミュニケーションを図り、各企業のニーズとHEREとしての事業や開発ロードマップと歩調を合わせながら、三菱商事の思いや戦略もしっかり反映させていく、といったことに取り組んでいます。HEREの基盤上で多様なサービスを構築してもらうパートナーエコシステムを形成するため、プログラムの設計やマーケティング施策にも着手しています。
 HEREインドオフィスにて。HERE、デジタル戦略部の皆さんと
HEREインドオフィスにて。HERE、デジタル戦略部の皆さんと具体的には、HEREのプラットフォーム上でどのようなサービスを作っていくのですか?


自動車産業で磨き上げたHEREの強みを活かし、自動車産業の変革とその先にある協業分野として、物流の最適化、都市交通の最適化(MaaS=Mobility as a Service)、マーケティングを通じた新たな顧客体験の提供に取り組みます。さらには、新たな金融サービスや都市開発、マイニング(鉱山オペレーション)の最適化といった、中長期的にDXが進む産業への展開も目指しています。
例えば、物流オペレーションの最適化では「共同配送オペレーション」の実現などに取り組みます。EC物流を中心に物量増や再配達問題が顕在化し、B2Bでも物流コストの増加や積載率の向上が業界全体の課題です。車両動態管理や荷物・車両のマッチングなど、複雑なオペレーションのための高度なアルゴリズム(配送計画の最適化や車両ルーティング等)が必要で、HERE基盤を活用した実証準備を進めています。
MaaS領域では、どのように取り組むのですか?


位置情報を起点に、三菱商事やパートナーの知見・事業基盤も組み合わせながら、モノやヒトの動きを可視化し統合できれば、産業面で大きなインパクトになると思っています。
MaaSには、移動手段を提供するプレーヤー、決済の仕組みなども含めてよりスムーズな人の移動をサポートするプレーヤー、サービス基盤を提供するプレーヤーなどさまざまな類型があります。そうした幅広いMaaSプレーヤーがサービスを提供するためのオープンな基盤をHEREとともに構築し、地域の交通課題の解決に貢献したいですね。まずは会津若松で、現地の交通事業者や店舗・施設と連携しながら、MaaS起点で暮らしの利便性を高める取り組みを始めます。


仕事を「自分ゴト」に。「考える」ことから始めよう

今日改めて感じたのは、大橋くんのように、仕事を自分ゴト化して、もがきながらも楽しく働くには、やはり「自分で考え抜く」ということに尽きるのではないかということです。決まったものを実行するだけでは「やらされ感」が出てしまう。特に組織が大きいとそうなりやすい面がある。自分の中からひねり出したアイディアを発信し、周囲の理解と共感を得ながら実行する。この一連の流れを踏むことが大切だと思いました。こういうマインドを持って仕事に臨めば、その結果の如何に関わらず、達成感ややりがい、成長実感を感じ取ることが出来るのではないかと思っています。
私も、産業DXを構想し実行する上では、顧客やパートナーの「そうなんだよね」を引き出すストーリー作りが重要だと感じます。そのためには、誰の課題を解決するのかという構想の基本をぶらさない。課題認識と解決策は自分自身でひねり出す必要があると思っています。私自身、ゼロから支えてくださった顧客やパートナー運送会社、メタノールチームの皆さんに少しでも早く恩返しができるよう、突破口を切り拓き続け、サービスを磨き込んでいきたいと思います。


僕はHERE事業への挑戦が、次の三菱商事の姿を示すことにもつながると信じています。それほど責任がある大きなチャレンジをさせていただいている、この環境や仲間、諸先輩方、社外パートナーの皆さんに感謝しつつ、最大限の貢献をしていきたいです。大橋くんとは同期かつ良きライバルとして、三菱商事と世の中を全力で盛り上げていきたいですね。