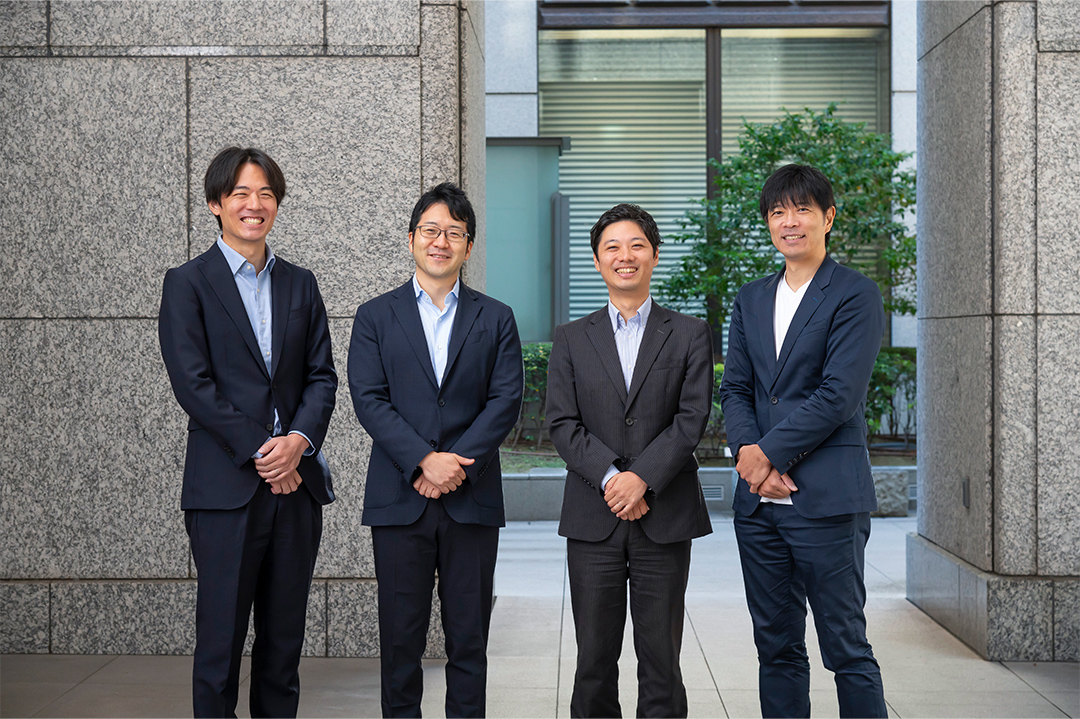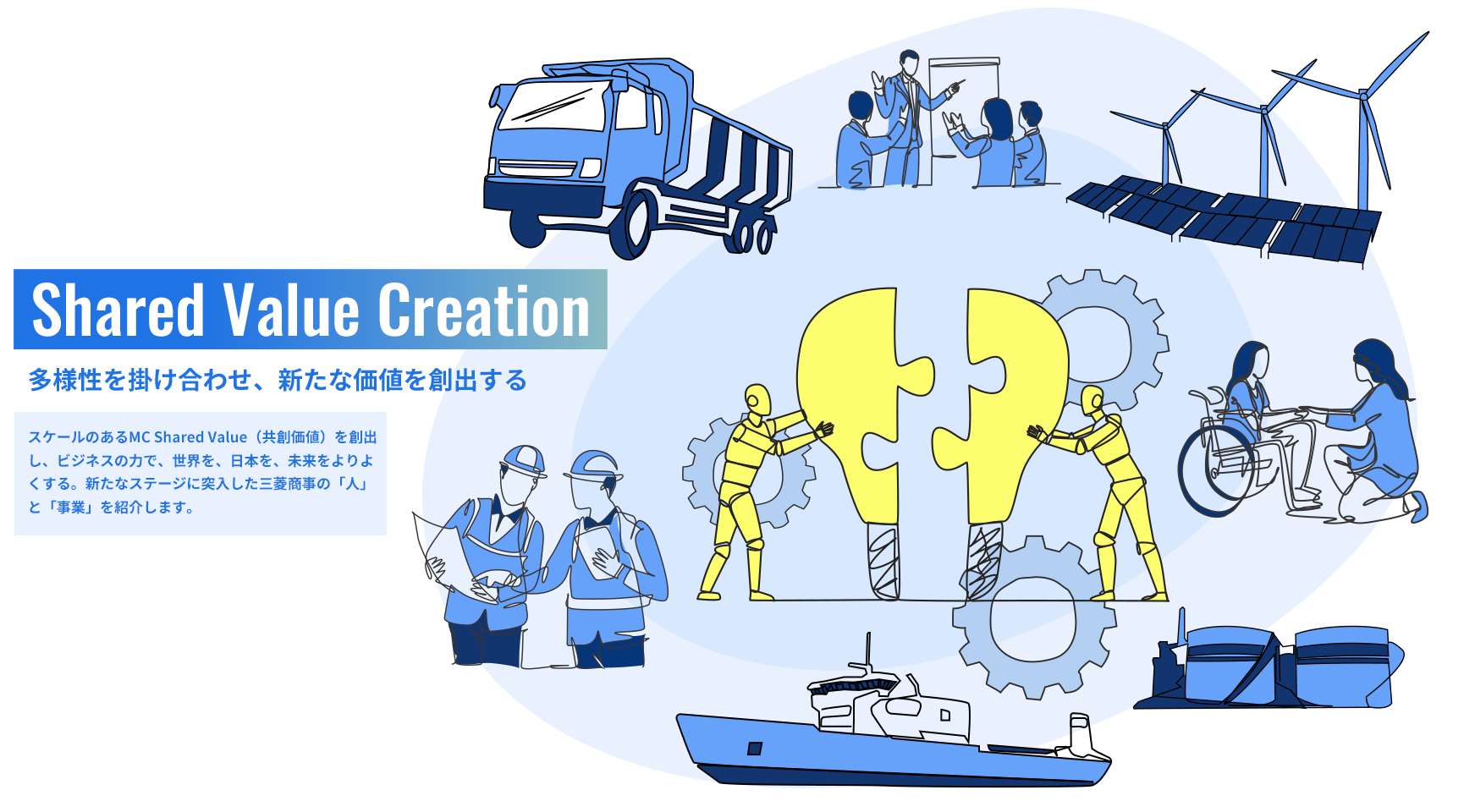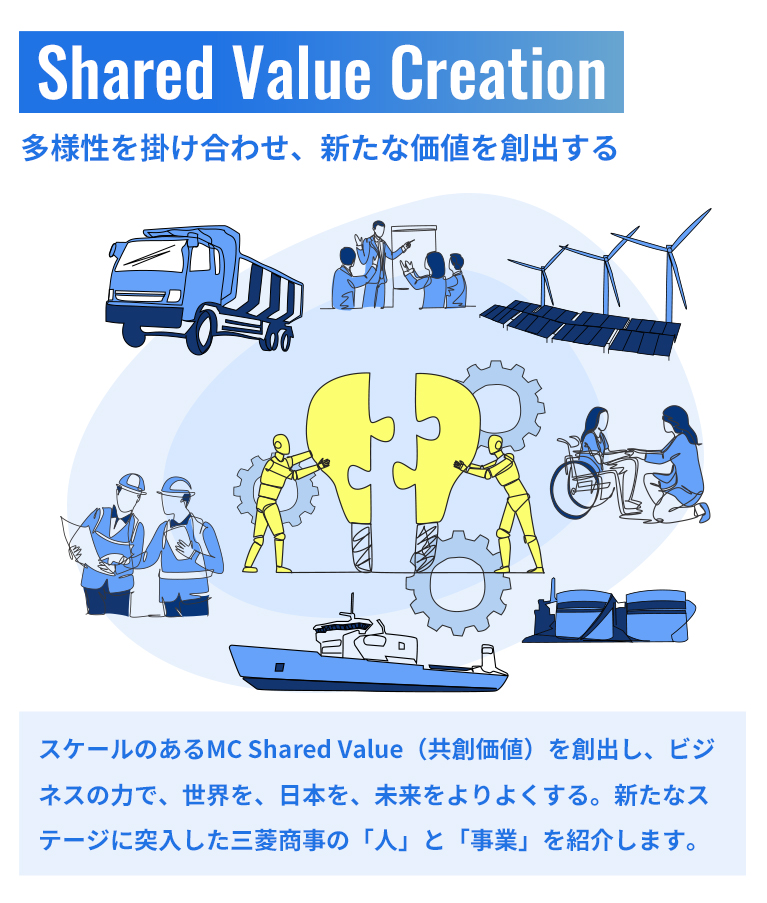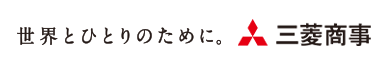「フィリピンの人々の生活を一変させた」と近年注目を集めている金融スーパーアプリ「GCash(ジーキャッシュ)」。2024年10月、三菱商事はアヤラ・コーポレーション(AC)と提携し、ACベンチャーズ・ホールディングスを通じて本事業への出資参画を発表した。フィリピンを舞台に新たな事業開発に挑むこととなったS.L.C.グループ金融事業本部デジタル金融事業部の社員に、朝日新聞GLOBE+の関根和弘編集長が、金融ビジネスを基盤に様々な「C to B」事業を創り出そうと奔走することのやりがいや、挑戦について聞いた。
-

鈴木 徳一郎 氏
金融事業本部
デジタル金融事業部
総括マネージャー 兼 リテイル本部 戦略企画室 -

中村 隼人 氏
金融事業本部
デジタル金融事業部
マネージャー -

松村 俊彦 氏
金融事業本部
デジタル金融事業部
マネージャー
※本文は敬称略
[聞き手] 関根 和弘(朝日新聞GLOBE+編集長)
新たな“生活のインフラ”になりつつある「GCash」
—— 座談会の前半では、デジタル金融市場の現在地、そしてフィリピンを席巻する金融スーパーアプリ「GCash」についてご紹介いただきました。後半ではまず、なぜ三菱商事がGCashの事業に出資参画したのか、その背景から教えてください。

鈴木 GCashは、フィリピン国民の8割近い約9400万人もの人が使用している、日々の支払いや送金に使われるスーパーアプリです。 GCashの広がりによって、これまで銀行口座を持つことが難しかった多くの人々が、自身の所持金を正確に把握できるようになり、貯蓄・投資の機会が増えました。また、これまでは「会社を起こしたい」「子どもの教育資金を借りたい」といった場合も、親族からお金を借りるか、いわゆる市中の高利貸から借りるしかない状況でしたが、GCashが提供する融資商品によって、多くの人が適切な金利でローンを組むことができるようになりました。このように、GCashはいまや、フィリピンの人たちの暮らしの質を向上させる、「新しい生活インフラ」のような存在になりつつあります。 すべての人が金融サービスに平等にアクセスできる「金融包摂(ファイナンシャルインクルージョン)」という考え方は、貧困の削減や所得格差是正のために重要であるとして、SDGs(「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核をなす17個の国際開発目標)の観点にも合致します。GCashの普及は、まさにこの金融包摂の実現に貢献するものであり、三菱商事がその支援をすることには大きな社会的意義があると思っています。
—— 社会的意義に加え、三菱商事にとっての経済的なメリットも大きいわけですよね。
鈴木 そうですね。出資参画をする以上、その経済的なリターンは当然見込んでいます。その際、フィリピンの「経済成長」、そして「キャッシュレス決済化」の動きが、GCash事業のさらなる追い風になると考えています。 フィリピンの平均年齢は26歳くらいの“若い国”です。また、2030年にはGDPがASEAN諸国で第2位に達するという予測もあります。一方で、フィリピンでの支払い手段を調べると、約7割はいまだ現金決済です。キャッシュレス決済の市場潜在性が大きいともいえるでしょう。 フィリピンの著しい経済成長と今後のキャッシュレス化の波を捉えるとともに、GCashのさらなるサービス向上に取り組むことで、この事業をより一層成長させていくことができると考えています。
—— GCash事業には、フィリピンの大手財閥も関わっているそうですね。
鈴木
200年近い歴史のあるフィリピン最大級の財閥企業、アヤラ・コーポレーションです。アヤラ・コーポレーションは、不動産や金融、通信、電力、自動車、ヘルスケアなど多角的な事業展開をされており、三菱商事とは1974年から50年間にわたって、モビリティ、インフラ等の幅広い分野で協業するなど、良好なパートナーシップを築いてきました。
アヤラ・コーポレーションのグループ会社の一つに、グローブ・テレコムという通信会社があり、GCashプラットフォームを運営するグローブ・フィンテック・イノベーションズ(GFI、通称Mynt<ミント>)の株も保有しています。アヤラ・コーポレーションと様々な協議を進める中で、このGCash事業を一緒にやっていこうという話が持ち上がり、この度、GFIの株主であるACベンチャーズの株式50%を三菱商事が取得する構想に至りました。
我々にとっては、異国の地・フィリピンでの事業、それも「C to B」*の金融事業という新たな領域での事業ですから、アヤラ・コーポレーションとともに新たな機会が得られたことを非常に心強く思っています。
*三菱商事では、一般的に用いられる「B to C」ではなく、「C to B」という表現を使用している。これには「生活者のニーズに向き合い、生活者のニーズを起点にする」という考え方が込められている。
アプリを超えた協業の可能性も模索しながら
—— 三菱商事が出資参画することによって、GCash事業は今後どのように進化・深化していくのでしょうか。また、アヤラ・コーポレーションとの協業という点ではどんな展望を描いていますか。

鈴木 前半でもお話しした通り、GCashは、キャッシュレス決済やローンなど、いまのフィリピンで最も求められている基本的な金融機能にフォーカスすることで、圧倒的なダウンロード数を記録しています。ただこのGCashの事業には、まだまだ発展の余地があると我々は考えています。 その第1段階は、「GCashの高付加価値化」です。生活者向けには、金融以外の多種多様なサービスの拡大、ユーザーエクスペリエンスの向上などが、今後求められるようになっていくでしょう。 事業者向けにも、共通ポイントサービス「Ponta」のノウハウや、MCデジタルをはじめとする事業会社が有する機能など、我々に期待されている領域が多々あります。例えば、決済の履歴から「こういう生活スタイルの、こんな属性の人」といったペルソナを作成し、より有効なターゲティング広告を展開できるようにする。顧客の分析や在庫管理のためのツールを提供する。AI(人工知能)を用いたマーケティング等の機能を搭載する、等々。三菱商事のノウハウ・知見を活用することで、GCash事業の価値をより高めていくことができると考えています。 続く第2段階では、GCashの顧客基盤を生かして、「生活者向けの様々な事業」をアヤラ・コーポレーションと立ち上げていきたいと考えています。
—— まずは、GCashに新たな付加価値を提供すること、さらにその顧客基盤を活用した別の事業展開も視野に入れているということですね。
鈴木 その通りです。さらに第3段階では、S.L.C.グループ以外の三菱商事の様々なグループがアヤラ・コーポレーションとともに事業開発をできたらと思っており、可能性は多岐にわたります。 実はすでにアヤラ・コーポレーションとは、GCash事業を機に「フィリピンの経済発展に資する、包括的な協業を進めていく」というビジョンを共有しています。多種多様な産業に広い接地面を有する三菱商事と、フィリピンで長年幅広い事業を展開してきたアヤラ・コーポレーションならではの、有意義な連携ができることを楽しみにしています。 とはいえ、いまは第1段階がやっと始まったばかりです。着実に一歩ずつ取り組んで結果を出し、いずれフィリピンの経済発展に貢献できるような存在になれたらと思っています。
ともに事業を作る 大事なのは「信頼」
—— 元々、国内を中心とする食品・小売り関連の事業を特に強みとしてきたS.L.C.グループが、フィリピンでのデジタル金融事業に乗り出すというのは、困難や挑戦も多いのではと推察します。いかがですか。

松村 そうですね。プレスリリースなどには「フィリピン最大の金融アプリに出資参画」などと書かれているので、一見華々しいプロジェクトに見えるかもしれませんが(笑)、ここまでの過程は、ある意味、とても“泥臭い”作業の積み重ねでした。 投資や事業の慎重な精査(デューデリジェンス)を経て、社内で検討に検討を重ねて最終決裁を取り付け、先方との交渉・契約を進める──。一つとして取りこぼすことのできない作業を、鈴木さんを筆頭にチーム一丸となって着実に積み上げてきた、といった感じです。 振り返ると本当に大変な道のりでしたが、ここからが新たなスタートです。さらに気を引き締めて、皆で取り組んでいきたいと思っています。 中村 三菱商事は世界各地で多様な事業を展開しており、フィリピンにおいても、インフラや再生可能エネルギー、自動車など、すでにいくつもの事業に取り組んでいます。ですが、我々が取り組んでいるC to Bの金融事業は、いまだ未知の領域。「日本での知見が実際どれくらいフィットするのか」などと悩みながら、検討を進めているところです。現地の市場調査など、あらゆることをゼロから進めていく大変さと面白さを感じながら、日々仕事に取り組んでいます。 鈴木 商社の仕事の面白みの一つは、「事業投資先の現場で、ともに事業を作っていく」ことだと常々思っています。ですが当然、現場では色々な人間関係があり、色々な事態が巻き起こるものです。私がどこの国・どこの現場でも、最も大事にしてきたのは、「相手の信頼を得る」ことです。 では、どうすれば信頼を得られるのか。その方法は、目の前の事業の成功のために「誰よりも汗を流す」こと以外にないと思います。先ほど、アヤラ・コーポレーションと50年にわたる深いお付き合いがあるとお話ししました。これは先人が築いてきた信頼関係があってこそ。この三菱商事との関係性を、さらにつなぎ深めていきたいです。それができるかは、まさにこれからの私の努力次第だと思っています。 三菱商事は様々な事業投資を行っていますが、新たな分野へのこの規模の投資は久々です。各方面からの大きな期待とプレッシャーをかみしめながら(笑)、これからも力を尽くしていきます。
次の時代の“当たり前”を生み出せる存在に
—— 最後に、皆さんが仕事を通して実現したい思いや、今後の夢についてお聞かせください。

中村
私は「国の成長を支援する仕事をしたい」という思いを持って仕事をしてきましたが、このGCash事業はまさに、フィリピンの成長に貢献できる案件だと捉えており、大きなやりがいと責任を感じています。
金融ビジネスの形は時代とともに変わっても、この仕事に携わる人の根っこには、変わることなく「人の挑戦を支えたい」という思いがあると感じます。個人や企業の挑戦に伴うリスクに対して、銀行はお金を貸すし、保険会社は保険商品を提供する。そうやって多くの人の「挑戦」を後押しすることが、結果として「国の成長」にもつながっていくのだと、いまあらためて実感しています。
松村
私は中途入社で、前職では化粧品会社のデジタルマーケティングやDXの仕事を担当していました。このGCashの案件は、データを活用してアプリ内の顧客体験を向上させることで、フィリピンの人々のニーズに応え、生活を改善できるので非常にワクワクしています。
というのも、デジタル決済は数カ月に1度使用するようなものではなく「日常的に」使うことが一般的なため、データとしての鮮度・頻度が非常に高いと考えています。また、「商品ジャンルや店舗の枠を超えて」多様なデータを収集できます。これらを活用して新たな事業を作っていくことは、難しい半面、とてもやりがいがあります。もちろん、これらを行う際には、ユーザーのデータプライバシーを維持し、関連する法令等を順守することが重要です。いま私たちが当たり前に利用している様々なサービスも、ひと昔前は存在していなかったので、次の時代の“当たり前”はぜひ我々が作り出していきたいと考えています。
また、個人的な思いとしては、未来の世代が、「いまより、もっといい社会」で幸せにくらしてほしいなと願っています。そのために目の前のことを一つずつ、まずはフィリピンをさらに「いい社会」にしていくための一助となれるよう、尽力していきたいと思います。

鈴木 私は「事業を作りたい」と三菱商事に入社して以来、共通ポイントサービス「Ponta」の立ち上げ、アメリカでのベンチャーキャピタル立ち上げ、ローソン銀行の立ち上げ、ヘルスケアのベンチャー事業開発など、まるで鉄砲玉のように(笑)、色々な現場に行っては様々な事業開発に取り組んできました。 私が事業開発の仕事が好きな理由は、その商品・サービスが社会に価値・意義を提供するものである限り、世の中にずっと残り、価値を提供し続けるから。つまり、利用してくださる人やそこで働く人のくらしをずっと支えていく存在になり得るからです。GCashもまさにそんな事業へと成長していく可能性を秘めており、とても意義のある仕事だと思っています。 日本は少子高齢化・低成長の時代といわれますが、成熟した国家ならではの多方面の蓄積があります。日本と、経済成長著しいフィリピンとの「架け橋」として三菱商事が機能することで、両国が互いに補完し合いながらそれぞれの成長を遂げていく──。そんな明るい未来像も思い描きながら、日々の仕事に励んでいます。