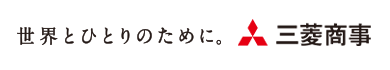Connecting to the future:いまの自分に出せるバリューは何か? 国内外の現場で鍛えられ、育まれた使命感
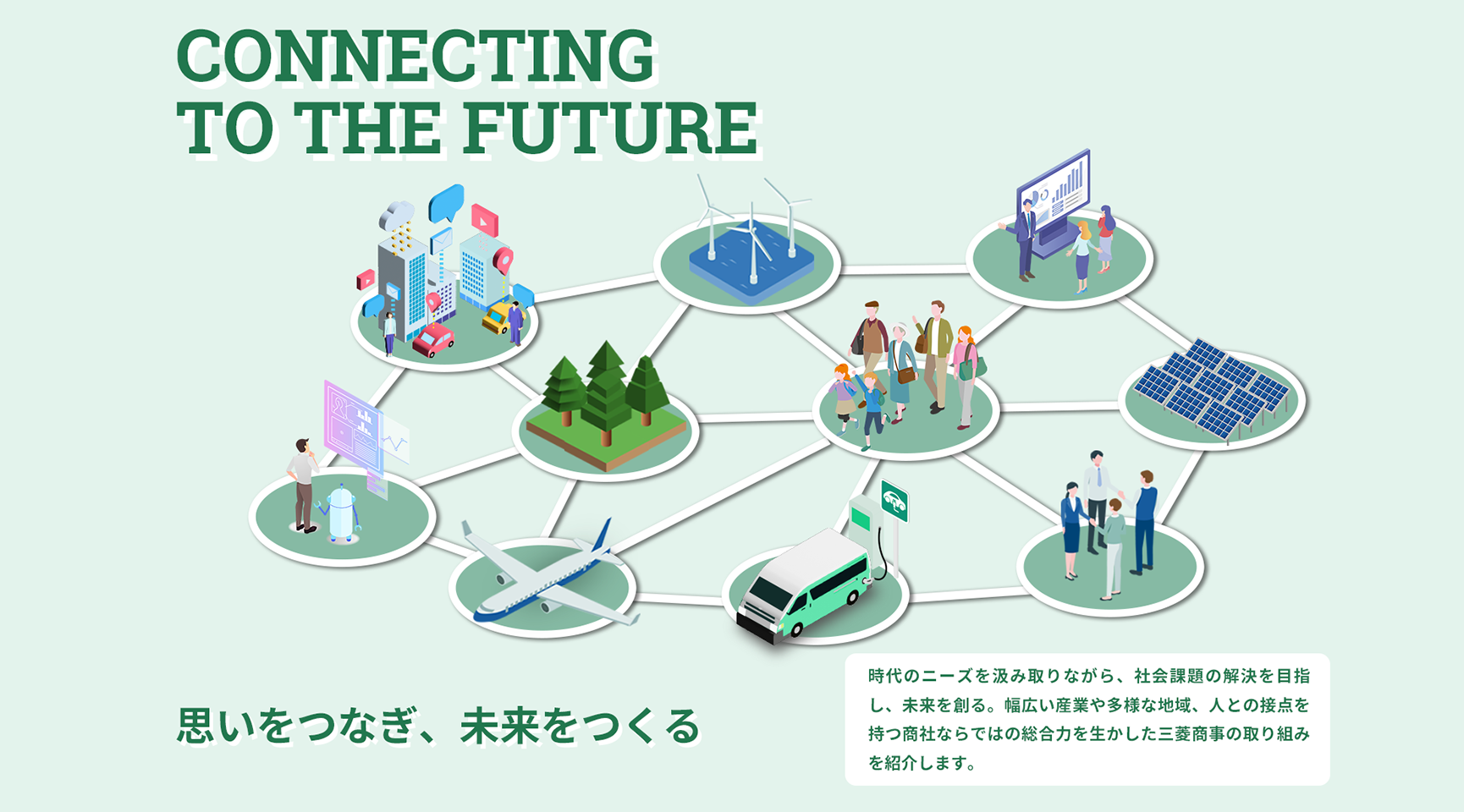
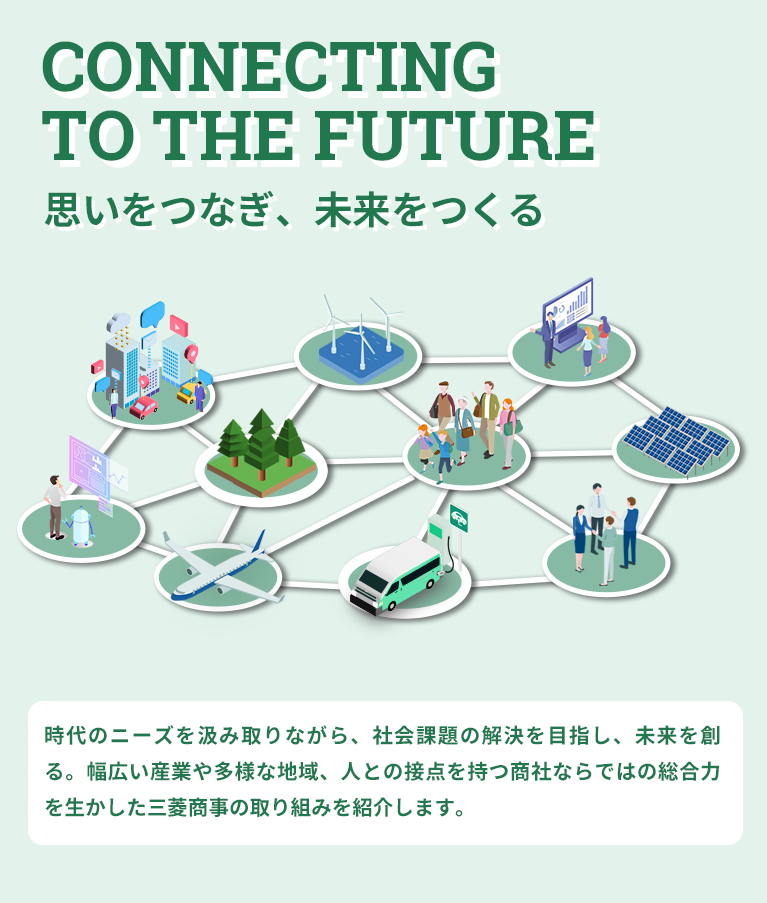
多彩・多才な人材が未来をつくる vol.1
いまの自分に出せるバリューは何か?
国内外の現場で鍛えられ、育まれた使命感

世界中に広がる拠点と約1,700の連結事業会社と協働しながら、幅広いビジネスを展開している三菱商事。その競争力の源泉である人材を、三菱商事はどのように育成しているのか。社員は個々の力をどのように磨き上げ、日々の仕事に向き合っているのか。
シリーズ第1回は、異なる領域で奮闘する3人の中堅社員が登場。三菱商事で働く醍醐味(だいごみ)や面白さ、苦労、そして今後の夢を語り合った。(聞き手=GLOBE+編集長・関根和弘)
- [ 座談会参加者 ]
-
平井 良樹 氏(ホワイトヘルスケア 保険者事業部 部長/三菱商事から出向)
渡辺 千春 氏(複合都市開発グループ 都市インフラ本部 国内事業開発室)
小池 大佑 氏(サウディアラビア・リヤード駐在事務所 自動車・モビリティ部 Assistant Manager)※座談会にはオンラインで参加
※本文は敬称略 - [ 聞き手 ]
- 関根 和弘(GLOBE+編集長)
医療、街づくり、自動車……最前線の現場で活躍中

—— 今日は入社6〜9年目のお三方に集まっていただきました。まず仕事内容を大まかに教えてください。
平井 医療・介護・予防の分野で様々な商品やサービスを提供している、コンシューマー産業グループへルスケア本部に所属しています。2020年には、三菱商事と東京海上ホールディングスによる合弁会社、ホワイトヘルスケア株式会社の設立に携わり、いまは同社に出向して4年目。事業責任者を務めています。 ホワイトヘルスケア設立の背景にあるのは、日本の深刻な社会課題の一つ「医療保険財政の逼迫(ひっぱく)」です。高齢化に伴う疾病構造の変化によって国民医療費は年々増加し、現行の皆保険制度は、いずれ立ち行かなくなるとの見方もあります。 そこで私たちは「医療費の適正化」と「病気の予防」の両立を目指し、レセプトデータ(診療報酬明細書)などの医療データを活用して、適正化の余地のある医療費にアプローチをする事業を行っています。分かりやすいところで言うと、医療データに基づいたOTC医薬品(医師の処方箋<せん>なしで購入できる市販薬)の提案をはじめとする医薬品の適正使用の推進や、医療機関を巻き込んだ様々な取り組みを、健康保険組合や自治体、地域の医療機関向けに開発・展開しています。社会課題の解決を目指した事業をゼロから立ち上げている最中、といった感じですね。 渡辺 私は、複合都市開発グループの都市インフラ本部国内事業開発室に所属しています。本グループでは、単なる不動産開発を超えて、エネルギーやモビリティ、ヘルスケアなど三菱商事の総合力を生かした「都市開発・都市運営」を展開することを目指しています。 いま私が担当しているのが、神奈川の藤沢・鎌倉エリアの大規模な再開発案件です。都市運営のメニュー考案と同時に、開発プランの作成や関係者への提案を行っています。

小池 1年半前からサウジアラビアの首都リヤードに駐在し、リヤード駐在事務所 自動車・モビリティ部にてサウジアラビア、バーレーン、イエメンにおけるいすゞのピックアップトラックとSUV(スポーツ用多目的車)の販売支援、さらに中東全域のマーケティング戦略・施策の立案・実装を担当しています。 中東市場における自動車販売台数の約5~6割を占めるサウジアラビア市場では、とくに日本車のプレゼンスが高く、最近はサウジアラビア政府が経済の多角化を目指して推進する各種政府系プロジェクト向けの建設需要を中心に、主力商品であるピックアップトラックの販売が好調です。中国ブランドなどの参入も相次ぎ競争が激化する中、中長期的な競争優位を保つべく、現地のスタッフらとともに頑張っています。

キャリア形成を後押しする、密なコミュニケーション
—— 入社してからこれまでは、どのような経験をしてこられましたか。
平井 私は学生時代に社会保障制度に関する研究をしていたこともあり、ヘルスケア領域で仕事をしたいという強い希望がありました。入社後はまず、管理部研修生(※)として、財務・経理・コーポレート系の仕事を約3年間経験し、ヘルスケア本部には、入社4年目のタイミングで異動がかないました。 ※管理部研修生:若手社員が、財務会計や簿記など実務を担うプロフェッショナルとしての基礎スキルを総合的に習得できる制度。 渡辺 私も入社後は、平井さんと同じ管理部研修生に選ばれました。その後入社3年目に、希望していた不動産私募ファンドの運用会社に出向し、7年目にはアメリカの不動産投資会社にグローバル研修生(※)として派遣されました。同じ複合都市開発グループ内ながら、不動産・金融から新規事業開発まで幅広く担当することができ、学ぶことがとても多いです。 ※グローバル研修生:若手社員を対象に、海外での実務研修、海外のビジネススクールへの派遣、世界各国の文化と言語を習得するための語学研修を実施。 小池 私はもともと、消費者の顔が見えるような商材を扱いたい、そして早い年次から海外の現場で仕事がしたいという思いがありましたので、自動車・モビリティグループはまさにピッタリの配属先でした。入社2年目でグローバル研修生としてインドへ赴任し、事業会社での業務を経験した後、4年目の終わりからサウジアラビアに駐在して働いています。
—— とても順調にキャリアを重ねているようですが、配属希望などについて、人事担当者や上長と話す機会などがあるんでしょうか。
平井 そうですね。人事の人が「君はヘルスケアがやりたいんだよね?」と入社当初から把握してくれていましたし、異動の時期が近づいてくると直属の上司も相談に乗ってくれました。三菱商事の人事は、社員に寄り添い、できる限り配慮してくれているという印象です。 小池 同感です。キャリア形成については、上司とじっくり話をする「成長対話」という場が年1回設けられているほか、それ以外でも「今後どうなっていきたいのか」「そのために実務でどんなことを担当したいか」といった相談を日常的にできる風通しの良い環境です。また人事担当から「あなたの希望するキャリアなら、こんな選択肢もありますよ」といった俯瞰(ふかん)的なアドバイスを受けることもあり、とてもありがたいですね。 渡辺 全社を管轄する人事のほかに、各営業グループにも人事担当者がいるので、それぞれの事業内容や現場の状況をきちっと把握したうえで「このグループにいま必要なのはこういう人材」と、判断してくれているように思います。もちろん、全員の希望がかなうわけではありませんが、その場合でも「キャリア形成の一環として、こういう力をつけてほしい」といった指針が示されるなど、手厚く対応してくれていると思います。

—— 渡辺さんは、グループ内で複数の部署を兼務されていると伺いました。
渡辺 三菱商事では2023年夏から、社員のキャリア自律を促すための新たな制度「デュアルキャリア制度」(就業時間の15%を上限に、希望に応じて別の仕事ができる仕組み)が導入されました。 私はそのグループ版の施策である、グループ内「デュアルキャリア制度」の募集を見て「やってみたい!」と手を挙げまして、現在、複合都市開発グループ内ベンチャー投資を検討する部署の仕事もしています。農業や植物、宇宙といった様々な分野の有望なベンチャーの技術やアイデアが、いずれ本務の街づくりやグループの事業に結びつくかもしれない、と想像力を働かせながら投資先・協業先を探索しています。忙しくはなりますが、新たな視点を得られますし、他部署の人と仕事ができるのもいい経験になっています。
「目指す姿は?」「本質は何?」 常に問いながら

——日々の仕事において、大切にしているモットーや心がけていることは。
平井 三菱商事で事業を進める上では、どんな領域であれ、知識も経験も自分をはるかに上回る専門家の方々と相対することになります。 例えば、私の担当するヘルスケア分野では、医師や薬剤師、厚生労働省が相手ですから、専門的な知識という面で勝てるわけはないですよね。そんな中でどうやって自分の役割を見つけるか、いかに信頼を得ていくかということは、すごく悩みました。 渡辺 よくわかります。どの業界にもその道のプロがいますからね。私も「アメリカの物流不動産一筋40年!」「首都圏のオフィス不動産一筋50年!」といった人たちと仕事をしてきましたが、もうかなうわけがない。 平井 そういう時に私が大事にしているのは、こういう世界・社会を作りましょうという「ビッグピクチャー(全体像)」を、誰よりも真剣に描くということです。「未来の医療制度ってこうあるべきですよね、そのためにはこういうことが必要なんです、だから一緒にやっていきましょう!」と明確な青写真を描くとともに、周囲の人を巻き込んでいくというのは、必ずしも専門家でなくてもできることだと思います。そのための情報収集や分析には、時間と頭を使っているつもりです。 渡辺 私の場合は「このビジネスが目指すところは何か」「三菱商事が取り組む意義は何か」という部分を常に意識するようにしています。こうした「本質をつかむ力」は、様々な領域で多様な専門家やスタッフと連携して仕事を進める三菱商事の社員に、欠かせないスキルの一つだと思います。私はいま新入社員のインストラクターもしていますが、「結局、何が大事だと思う?」「本質は何?」ということはよく問いかけていますね。 小池 私も中東に来たばかりのころは、「また新しい若者が日本から来たのか」という目で現地スタッフや自動車販売店の方々から見られるわけですから(笑)、苦労もプレッシャーもありました。1年目はとにかく、中東独特の自動車業界の特性を経験の長い上司や現地スタッフから学び、スポンジのように吸収することを大事にしていました。 ただやがて、経験豊富な同僚、販売店のスタッフであっても、把握している情報が不十分な場合があることがわかってきました。これでは正確な市場理解をもとに効果的なマーケティング戦略を立て、施策を打つことは難しいと考え、私は「誰よりも一次情報を取りに行こう」と、時間を作って自動車スーク(市場)に通い詰めるようになりました。 中東では、商習慣としてディーラーだけでなくスークでも自動車が売買され、競合の動向や消費者の声など様々な情報を拾うことができます。スークでは英語が通じないため、現地スタッフの支援やアラビア語の翻訳アプリも駆使しながら、スークの販売員から直接話を聞いてまわり、情報を収集・整理、蓄積していきました。販売店の担当者と会う際には、市場の事を聞く前にまず私から有益な情報を提供し、「彼は市場をよく見ていて情報を持っている」という印象を持ってもらうことを目指しました。これを続けていると、対面する担当者からも徐々に信用を得て有益な情報が自然と集まるようになり、パートナー達との深い信頼関係に繋がっていきます。一次情報に定期的に触れているので、周囲の人の中で誰が信頼できる情報を持っているかがよく分かってくるんですよね。 これからも分からないことは「他者から謙虚に学ぶこと」、その中でも「自分ならではのバリューを生み出すこと」の両方を大切に、愚直に努力を重ねていきたいと思っています。

—— なるほど。皆さんそれぞれの方法で、三菱商事の社員として果たすべき役割を全うしようと努力しているのですね。
渡辺 もちろん、日々の業務では地味な作業もたくさんありますよ。「どうすればこの価格に収まるか」とエクセルと終日にらめっこする日もありますし、取引先を何度も訪ねても、話が思ったように進まないなど……。細々とした苦労は多々あります。
平井 僕もまずはお客さんが主催する勉強会に参加して積極的に質問したり、オンライン会議に不慣れな人がいたら設定を手助けしたりと、一歩ずつ信頼関係を築くことから始めました。新規事業開発というと響きはスマートですが、実際は「地べたをはい回っている」感覚ですね。ただ、そういう積み重ねなくして、大きな目標に到達することはできないとも思っています。 小池 外から見えにくい部分でいえば、中東の宗教や慣習、そして複雑な歴史的背景を理解することは、やはり大変で勉強すべきことはまだまだ多くあります。その理解があってようやく、ビジネスのスタートラインに立てるという感じですから。
EX・DXが、産業を変える・地域を変える

—— 三菱商事は、中期経営戦略2024で「EX・DX戦略」をミッションに掲げています。皆さんの担当業務においては、具体的にどのような関わりがありますか。
平井 ヘルスケア・予防領域を例にすると、健保組合から健診や人間ドック受診の案内が来た際、「去年の結果がこうだったから今年はこれを受けよう」などと、検査項目や医療機関を能動的に選んでいる人はあまりいないと思います。でももし、個々のリスクや健康状態等のデータをもとに、一人ひとりに合った検査のプランや適切な医療機関がリコメンドされるようになれば、より納得感を持って健診や人間ドックを受けられるようになると思いませんか。デジタルやデータの力で、患者が最適な医療サービスを選ぶようになれば、費用対効果の高い医療サービスが選択されるようになり、結果的に医療費も適正化されていくはずです。 DX(デジタル・トランスフォーメーション)とはこのように、データやデジタル技術を活用して「産業を効率的で最適な形に変えていく」ということだと認識しています。ユーザーの課題解決のみならず、産業全体の課題解決に挑むDXの推進にはとてもやりがいを感じています。
小池 EX(エネルギー・トランスフォーメーション)に関していえば、サウジアラビアは2060年までのカーボンニュートラル(CN)達成を表明しています。三菱商事の拠点としては、この地で50年超にわたり国営企業や民間財閥と幅広いビジネスを展開してきており、石油化学・自動車事業を中心とした事業者として今後どのようにサウジアラビアのCN目標達成に貢献していくか、拠点全体の課題として考えています。具体的には、サウジアラビアは石油だけでなく再生可能エネルギーも非常に競争力があり、それを利用した次世代燃料でサウジアラビア・日本・自動車業界のCNに貢献できないか、検討しています。
——複合都市開発グループでは、EX・DXの一体推進による「地域創生」はとくに深い関わりがありますよね。
渡辺 そうですね。EX・DXの推進による地域創生は、三菱商事の目指す姿を体現する重要なミッションと認識しています。その際、都市開発・都市運営のサービスによって、地域の課題を解決するとともに、エリアの魅力・特長を打ち出していくことが地域創生のカギになると思っています。 冒頭でお話しした藤沢・鎌倉エリアでは、「ヘルスケアMaaS(マース)」の実証・実装の場を目指しており、12月には、平井さんの部署と協力して、健康や運動、移動などに関する最先端の情報交換や体験ができる市民向けイベントを開催します。
「人としての成長」も実感 いい仕事をこれからも

——三菱商事では「イキイキ・ワクワク、活気あふれる人材と組織」の実現を掲げています。皆さんは、ご自身がイキイキ・ワクワク働けていると思いますか。
小池 そうですね。サウジアラビアの街中で、いすゞのピックアップトラックやSUVが走っているのを目にした時は、やはりいつもワクワクすると同時に、これだけいすゞ車のプレゼンスが高い市場の担当者として責任を感じ、身が引き締まります。また、いま我々の車両が数千台規模で使われている大規模な国家プロジェクトも進行中です。急速な発展を遂げつつあるこの国を陰ながら支えているという点は、大きなやりがいになっていますね。 平井 私もパッションを持って取り組める領域で、目指す未来を思い描きながら仕事ができるというのはとても恵まれていることだと思います。入社8年目ながら「上司は社長だけ」という裁量あるポジションで仕事ができることも、非常にチャレンジングで満足しています。 渡辺 気の置けない仲間とワイワイ仕事をして、「今日もよく頑張ったな」と日々思えるのは、実は幸せなことだなあと思っています。しっかり働いたらしっかり休む、というオンオフの切り替えもできていて、この前の休暇はヨーロッパ旅行に行きました。 以前の私なら英語力に自信がなく、慣れない土地でビクビクしていたでしょうが、いまでは英語も臆せず話せるし、知らない世界でも好奇心を持って思いきり楽しめるようになりました。海外勤務を含めた三菱商事での様々な経験が、人としても成長させてくれたように思います。
——最後に、それぞれの事業領域での目標をお聞かせください。
平井 いま、日本の年間の国民医療費は40兆円を超えています。この日本の医療を「価値に基づく医療(Value Based Healthcare)」へとアップデートし、医療保険財政の破綻(はたん)を食い止めること、持続可能な医療保険制度へと生まれ変わらせることが大きな目標です。そのために、民間の企業として貢献できることに注力してまいります。 渡辺 三菱商事の総合力を生かした都市開発・運営を通して、魅力あふれる街づくりが実現できるよう、担当業務をしっかりと遂行していきたいと思います。また、これからも後輩や先輩とみんなで元気に仕事をし、社会によいインパクトをもたらしていきたいと思っています。 小池 中東市場におけるいすゞ車のプレゼンスを守り、さらに発展させていくこと。そして、中東の発展に貢献することが重要なミッションだと思っています。また、100年に一度ともいわれる変革期にある自動車業界において、自分たちの強みを生かして新しいビジネスにつなげていけるよう、力を尽くしていきます。 今日皆さんと話して、幅広い産業との接地面がある三菱商事には、多種多様なノウハウ、知見、人材がそろっていることをあらためて実感しました。それらを最大限に生かすことができれば、創出しうる「MC Shared Value(三菱商事グループが生み出す共創価値)」は無限の可能性があるし、社会課題に対してより良いソリューションをもたらすこともできるはずです。 私は学生時代から「自分で限界を決めず、チャレンジし続けられる環境で社会人人生を送りたい」と思っていましたが、三菱商事はまさにそういう会社であり、そんな環境に身を置いて仕事ができることを心からうれしく思っています。これからも恵まれた環境で社会に貢献していけるよう頑張っていきます。
- 第2回は、金属資源グループの6人の社員による座談会の模様<前編>を紹介します。
-
多彩・多才な人材が未来をつくる vol.1
いまの自分に出せるバリューは何か?国内外の現場で鍛えられ、育まれた使命感 -
多彩・多才な人材が未来をつくる vol.2
ともに働く仲間や地域社会との「信頼関係」が、日々の原動力に
金属資源グループ座談会[前編] -
多彩・多才な人材が未来をつくる vol.3
ビジネスは「成功」するとは限らない でも、多様な経験が「成長」につながる
金属資源グループ座談会[後編