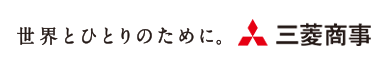AERA編集長レポート


パリ協定が示したCO2排出量削減目標を達成するための手段として、いま注目されているのがCCUS(Carbon dioxide Capture Utilization and Storage)。三菱商事でそのCCUSに挑むのは、それぞれ所属部署が違う、全社横断型のタスクフォースチームだ。今回は奥村龍介さん、小山真生さん、小﨑知恵さん、中村富郎さんの4人のメンバーに、三菱商事が取り組むCCUSの内容や、その展望などを聞いた。
-

奥村 龍介
北米三菱商事会社
シリコンバレー支店
エネルギー&カーボンマネジメント -

小山 真生
三菱商事株式会社
金属資源グループCEOオフィス
ローカーボンタスクフォース -

小﨑 知恵
三菱商事株式会社
天然ガスグループCEOオフィス
カーボンリサイクルユニット -

中村 富郎
三菱商事株式会社
総合素材グループCEOオフィス
事業構想・デジタル戦略ユニット

AERA 編集長
片桐そもそも「CCUS」という言葉がまだあまり浸透していないですよね。どういうことなのか、具体的に説明して頂けますか。
小﨑CCUSとは、地球温暖化の原因となるCO2を回収して有効利用(CCU)、または貯留(CCS)することを指します。CO2の排出を抑えるだけではなく、CO2を資源として回収して利用することで環境問題に取り組むと同時に、新しいビジネスを創出する。低・脱炭素社会実現のために期待されている技術です。
片桐CO2の回収や貯留というのは具体的にはどう行うのでしょうか。
小山回収は、工場の排気ガス等に含まれるCO2を化学反応を起こしたり、膜で濾過したりして取り除く方法があります。身近な例だと、炭酸飲料やドライアイスはCO2排出量の多い工場の排気ガスを使って作られているものなんです。実はもうCO2の再利用は実現できているので、問題は排出と再利用のバランスです。ネット排出量ゼロを果たすためには、CO2濃度が低い排気ガスからCO2だけを効率的に取り出すにはどうすればよいかがポイントになる。今はそこに取り組んでいます。将来的には大気中からのCO2の回収も可能になると思います。
- 脱炭素で先をいく欧米 カルチャーにギャップ -
菅首相は2020年10月の就任後初の所信表明演説で、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ネット・ゼロ宣言」を表明。業界の意識を「カーボンニュートラル」に向けた。三菱商事はCCUS事業の成功に向け取り組む。
片桐CCUSを成功に導くために必要なことはどんなことでしょうか。
小山やはり、雰囲気づくりですね。マーケットの意識やCCUから作られた製品のプレミアム感を醸成していくことは重要です。欧米ではすでに進んでいて、日本でもそこに近づくための第一歩が政府が発表したネット・ゼロ宣言だったと思います。今後、コストを下げていくためには技術の成熟も必要です。
奥村ネット・ゼロの難しさは、その先端をいくカリフォルニアなどでは相当前から言われていましたが、欧米の「難しいことをやるのがカッコいい」カルチャーと日本の「できないことは言わない」カルチャーとでは大きなギャップがある。日本人の場合、それが自分ごとになった瞬間にブレークするのではないかと思います。ゴミの分別をきちんとできる国民性をCO2の回収に生かせれば、日本は一気に変わるかもしれません。
片桐CCUSで、個人でもできることはあるのでしょうか。

小﨑サステナブルはカッコいい、と浸透させていく。
昨年までニューヨークにいたのですが、サステナブルファッションがすごく流行っていて、低炭素に取り組んでいるブランドの商品を身につけることはすごくクールなことだという意識が浸透していました。そうしたファッションで情報発信や意思表示をするのも個人でできることの一つだと思います。
小山ポップな人たちや最先端の人たちにインフルエンサー的にやってもらうと浸透するでしょうね。
中村私は先月までブラジルにいましたが、ブラジルでもサステナブルなことに取り組んでいる企業は多く、そうした企業を消費者が選んで意思表示するという流れもできていました。SNSを使ったビジネス戦略が上手く、日本も真似できることは多いと思います。
- CO2で衣類も究極のエコ社会が実現 -
片桐この仕事で、自分に、あるいは次の世代に、何が得られると思い描いていますか。また、やりがいを感じることや、大切にしていることは?
小山CCUSは未来を“究極なエコ社会”にすることができる、一つのアイテムだと思っています。CO2リサイクルで代用できる製品もある。例えば、ウォッカやアルコール消毒液、コンクリート、ポリエステル、ガソリンなど、意外となんでもCO2で作れるんです。我々がいま作ろうとしているのはコンクリートやポリエステル衣類、ペットボトルです。将来的にはガソリン車もCO2を回収・再利用したガソリンで走らせることが技術的には可能です。
中村CCUSを社会に広く流通させるための仕組みづくりから参加できるというのは三菱商事らしいなと思います。始めるところの発射点が低いというか、作り上げていくものが大きい。チャレンジの面白さも感じます。

奥村難しいからこそ、やる。
JFKのムーン・スピーチではありませんが「難しいとわかっているからこそやる」というシリコンバレー的とも言えるマインドセットはすごく大事です。チャレンジを誇りにしている部分もある。仲間とこの感覚が共有できているうちは大丈夫かな、と思います。
- CO2はいずれ静脈的にリサイクルも当たり前 -
片桐今の仕事が未来にもたらすものはなんだと思いますか?
奥村CO2のインフラは100年後にはもう当たり前で、当然ないと困る静脈的なものになっていると確信しています。例えば下水道って、紀元前2000年頃のモヘンジョ・ダロで最初に作られた時はものすごくイノベーティブなものだったと思うのですが、今ではあるのが当たり前になっていますよね。CCUSについても、100年後に、最初に取り組んだチームとして我々を思い出してもらえたら、ちょっとカッコいいかな、と思いますね。
小﨑日本人は「もったいない」というコンセプトが浸透しているので、CO2でもその意識が高まれば再利用が進むはずです。我々の仕事を起点に広まって、それが当然になっていたらいいな、と思います。
中村CO2が増えて温暖化が進めば、気候変動で住めなくなる地域が出てきたり、絶滅の危機に瀕する動物も増える。マイナスの変化を少しでも食い止め、環境問題に貢献できているという実感を持って働けるのはうれしいです。

小山ドミノの最初のひとつになれたら誇らしいと思う。
僕らの仕事が「CO2リサイクルは当たり前」というドミノの最初の牌になれば。本当にそれができたら誇らしいですよね。


※奥村龍介さんは米国シリコンバレーよりオンライン参加。
難しいからこそのチャレンジ。
シリコンバレー的マインドで「CO2ネット・ゼロ」に挑む
CCUSタスクフォースは三菱商事内のグループ横断型チームであることも特色のひとつだ。経験やバックグラウンドの全く異なる者同士でチームが結成されて2年。グループ横断型でチームが結成された経緯やメリット、その難しさや課題についても聞いた。
片桐なぜ、グループ横断的にチームを組んだのでしょうか。
奥村CCUSというものを考えたときに、新しい産業そのものなのではないか、と。既存のビジネスとは少し距離をおいて、まずはまったく新しい産業として進めてみたほうが結果的に最終形に近くなるのでは、と思いました。
小山知らない情報を知るためにも、他のグループの人とチームアップすることが必要でしたね。
- 仕事も働き方も新しい組織もイノベーティブ -
片桐奥村さんと小山さんがつながった最初のきっかけとは?
奥村東京の担当者にお願いして、僕のやってみたいことに詳しそうな人、興味のありそうな人全員と社内Zoomでつないでもらいました。そこで小山さんはじめチームの皆さんと出会いました。
小山このチームに参加してから、グループ外の人と話す機会のほうが多くなりました。上司の命令でなく、自発的な協力とか、何か面白いことやっていこうよっていう雰囲気がこの会社らしさ。結果的にこういうチームができたのも必然なのかな、と思います。
組織の壁を越えたチームの理由。
「イノベーティブな仕事にはイノベーティブな組織が必要」
片桐みなさん、お仕事をかけもちしているということでしょうか。
小﨑私は自分から希望してタスクフォースに参加したのですが、今は社内の理解もあり、この仕事をメインにさせてもらっています。
小山僕も途中から専任でやらせてもらえることになりました。
中村チームに入ったばかりですが、専任でやらせてもらっています。このようなチャレンジを会社としてもバックアップしてくれるのは、良いカルチャーだと思います。
片桐それぞれが専任でも、一つの部署にはしないのですね。
奥村それぞれ違う場所にいることがオープンでイノベーティブな発想につながる部分もある。成長余地がより広がるのではと思っています。
片桐やりにくさは感じませんか?
小﨑メンバーの仕事の状況は100%見えてこない。誰かがすごく忙しくて、マンパワーが足りないというときにも、気づきにくいですね。そこは定期的な会議や、周りを気遣うことでカバーしあっています。
小山ただ、今はテレワークが多くなり、所属が同じだからといって毎日会えるわけでもない。そういう意味ではグループの壁や縦割りなどはあまり気にならなくなってきています。
変化の激しい世の中で、産業の垣根を越えたビジネスもめまぐるしい勢いで生まれている。CCUSもまた、産業の垣根を越え、多くの業界関係者と関わるため、「総合格闘技」とたとえられる。多様な産業との接点を持つ三菱商事は、そのレンジの広さを十二分に生かせるという。
- CCUSは「総合格闘技」志を共に発信していく -
奥村最初、このチームを作るときに、どんな組織を設計したら、これから新規ビジネスを量産していくための再現性が生まれるかも議論しました。みんなスペシャリストですし、CCUSは総合格闘技なので、やっぱり機能的な組織にして、プロジェクトチーム体制にしよう、と思いました。
小山最初、10人ぐらいでチームアップしましたが、今はすでにカジュアルに意見交換する人は社内に100人ぐらいいると思います。

中村所属が違っても、同じ志を持つ同士の推進力がすごい。
タスクフォース内には上司部下の関係がないので、方向性が定まらず停滞することもあるのかと思いましたが、実際にチームに入ってみると、皆さんが同じ方向に向かって全力で進んでいる。非常にうまく機能しているな、と思います。
奥村僕らの仕事は面白いけれどやっぱりわかりにくい。発信力も大事だと思います。啓蒙的な「エバンジェリスト」の部分も求められている。今後の課題ですね。