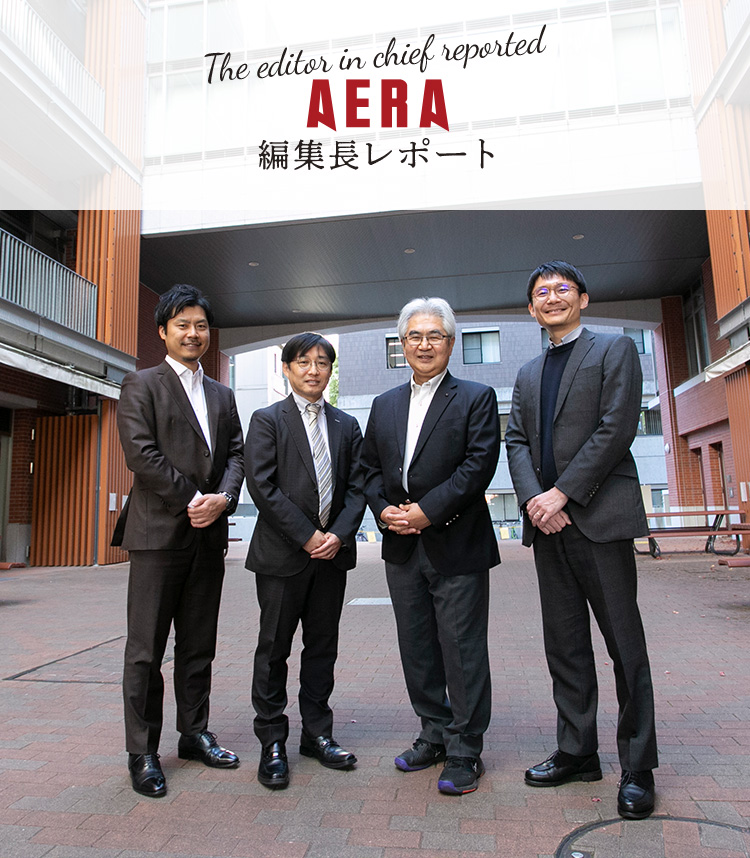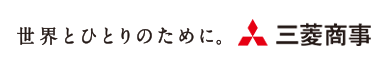AERA編集長レポート


三菱商事は京都大学と連携し、同大の研究成果を活用した起業支援プログラムを開始した。初年度に採択された7件のプロジェクトが、社会実装に向けて進んでいる。その全容について、本誌編集長の木村恵子が聞いた。
-

小林 輝樹
京都大学 産官学連携本部
スタートアップ支援部門 部門長
起業支援プログラムの制度設計から運営、各プロジェクトへの支援のほか、主に関西圏の大学で構成されるスタートアップエコシステム形成支援プラットフォーム「関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)」の運営も担う。 -

松浦 雄一
三菱商事 経営企画部
インテリジェンス室 課長
先端技術の調査・分析などを担当。産学連携では、民間企業視点からの技術評価や分析、事業創出のためのディスカッションを重ねている。 -

末廣 克尚
京都大学 産官学連携本部
知的財産部門
主に特許関連の支援を担当。知財を活用して研究資金を獲得し、研究を拡大していく戦略的方法などを、研究者と共に提案している。 -
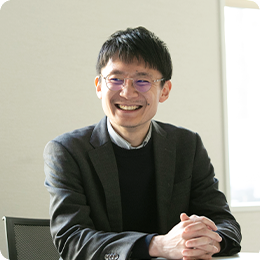
畠山 航
京都大学 産官学連携本部
スタートアップ支援部門 副部門長
(三菱商事から出向)
三菱商事で食品関連の新規事業開発などを担った経験を生かし、起業支援プログラムの運営・プロジェクトの伴走支援に携わる。
2023年4月に始動した『京都大学・三菱商事Startup Catapult(スタートアップカタパルト)』。27年度までの5年間の運営費に充てられるのが、三菱商事による総額6億円の寄附だ。起業をめざす同大の研究プロジェクト1件につき、年間最大2000 万円が支援される。プログラム名にある〝Catapult〞は「発射台」を意味し、「研究を社会実装に向けて勢いよく飛び立たせたい」との願いが込められている。その背景や支援体制、今後の展望などについて、京都大学の小林輝樹さんと末廣克尚さん、畠山航さん(三菱商事から出向中)、三菱商事の松浦雄一さんの4人に聞いた。

AERA 編集長
木村「スタートアップカタパルト」が新設された経緯について教えてください。

小林京都大学では2016 年度から、研究成果を社会実装につなげるための起業支援プログラムを実施してきました。これまでに採択されたプロジェクトから35社が創出されていますが、プログラムの運営資金を国の支援だけに依存せず、持続的な財源を確保することが課題でした。そんなときに三菱商事さんから連携のお話を頂いて。対話を重ねるなかで、本学の起業支援のあり方に共鳴いただき、6億円をご寄附いただくことになりました。


松浦三菱商事は世界各地で事業を展開していますが、そのベースは日本にあります。国内の科学技術の発展に貢献することで、日本の産業競争力強化、ひいては世界規模の社会課題解決につながればとの思いがありました。京都大学はノーベル賞を受賞した山中伸弥教授をはじめ、その研究力の高さや独創性は言うまでもありません。寄附のみならず、三菱商事の国内外のネットワーク・産業知見を提供することで、高い問題意識を持つ京都大学とともに、研究と社会実装の両輪を一緒に進められるはず。そうして連携に至りました。
木村6億円というのは、あまり聞いたことのない規模の寄附ですね。
小林金額もさることながら、大学と企業との産学連携でよくある共同研究では、研究テーマや成果物を決めた上での限定的な内容になりがちです。それを今回、寄附という形で支援いただいたおかげで、制度設計や審査過程も我々の裁量で行えますし、大学にとって非常に自由度が高いものとなっています。
松浦研究内容を指定した寄附だと、その研究は我々の想像の枠を出ません。自由な資金を提供することで、想像を超えた独創的な研究のサポートに貢献できればと思っています。
小林スタートアップの持続的な創出により、リターンとして研究資金を得ることができ、そこからまた新しい研究成果が生まれていきます。本学は関西圏の大学のスタートアップエコシステム(※)の構築の中心的役割も担っていますが、そうした循環型のシステムをつくることで、大学としても、新たな価値の創造や世界的な社会課題の解決に挑戦できます。
※自然界の生態系とその維持システムに由来し、ビジネスにおいて多様な企業がそれぞれの強みを生かして連携しながら、共存共栄を図ることを意味する
スタートアップカタパルトでは23年4〜6月に初年度の公募が行われた。19件の応募があり、学内での審査の結果、7件が採択された。採択されたプロジェクトのチームには、助成期間の1年間、京都大学産官学連携本部の専門支援人材等がついて伴走し、知財戦略などを含めたさまざまなサポートが行われる。
想像を超えた独創的な研究が
社会課題の解決につながる
シーズとニーズを見極め
最適な業界とマッチング
木村採択されたプロジェクトの内容や、支援体制について教えてください。

畠山一部を紹介しますと、例えば、バイオマス資源を燃焼させることなく、エネルギーを直接的に取り出す研究。発電を大幅に効率化できる上に、その過程で生まれる高濃度CO2は、さまざまな分野で活用が期待されています。また、地域ごとに住民の健康情報をデータ化して集約することで、ウェルビーイングの促進をめざす研究もあります。

末廣医療系ですと、京都大学の研究の代表格であるiPS細胞を使ってヒトの心臓組織を培養し、心臓病関連の創薬に役立たせる研究も。また、糖尿病性足潰瘍患者の治療のために、ヒト線維芽細胞からつくった細胞ブロックを活用する研究もあります。採択に至らなかったプロジェクトのなかにも、人文系を含めて多彩な分野の研究があり、いずれの内容もレベルの高いものでした。
畠山採択された研究課題だけでなく、申請をご検討いただいている研究プロジェクトに対しても積極的にご支援させていただきたいと考えています。事業化の過程では、ビジネスの〝種=シーズ〞と、それがどのような分野で求められるかという〝需要=ニーズ〞のギャップを埋めることが大切です。必要に応じて、三菱商事内の声も集めて、率直なフィードバックも差し上げています。意外な部署から「研究者とこうしたテーマでつながりたい」という問い合わせをもらい、つなぐことも。京大産官学連携本部の一員として、京大内の技術シーズをスタートアップという形で社会実装することを支援するのが私のミッションであり、その実現のため、研究プロジェクトの皆さまには三菱商事が持つ知見とネットワークをフル活用していただきたいと考えています。
末廣産官学連携本部では、特許申請や知的財産の管理、ライセンス交渉の支援など、知財サポートも行っています。特許出願のタイミングからトータルなビジネスプランを一緒に考えていきます。まずはスタートアップカタパルトを起爆剤としてもらい、特許も活用して、公的資金、ベンチャーキャピタル資金等の研究資金を得ることで、さらに研究をスケールアップしてもらいたいと思っています。
小林公募の前提として補足しますと、研究者は応募の際、研究を事業化できる人材と共に共同申請する必要があります。ただし、事業化のノウハウを持った人材は慢性的に不足しています。この人材を確保する部分でも、支援の仕組みづくりを考えているところです。
松浦大学は地域産業のエコシステムの核となる存在です。京都大学が強みとするエネルギーやライフサイエンス、素材などの先端技術と、弊社が中期経営戦略に掲げて取り組んできたEX(エネルギートランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)をかけ合わせれば、地域創生にも貢献できる。そうして国内を盛り上げていければ、日本の世界での存在感も高まるはずです。
先行き不透明な時代にこそ
先端技術への感度を高めたい
思いを共有しあい
大学と企業の輪を広げる
木村プログラム2年目に向けた意気込みや課題はいかがでしょうか。
小林まずは本プログラムの認知度を上げて、30件程度の申請件数を確保できるようにしたいですね。事業化できる研究を発掘することも必要です。プログラムの継続には、三菱商事さんのように賛同してくれて、味方となってくれる企業も増やしていきたい。他の企業からの資金提供も受け入れ、支援規模の拡大、運用期間の長期化を図っていきたいと考えています。
畠山スタートアップという形で研究を社会実装することにご関心がある研究者の皆さまに、カタパルトをはじめとした学内の起業支援プログラムの存在をまずは知っていただきたいと思っています。その上で、スタートアップを志向される方には最大限の支援をしていきたい。そして、小林さんのおっしゃるとおり、本プログラムは三菱商事と京都大学の間だけで閉じる必要はなくて、他の企業とのオープンイノベーションもあり得ると思っています。
末廣本学には、教員と研究員あわせて約4000人もの研究者がいます。その研究者たちが過去に何年もかけて生んできた研究成果があります。これから期待される成果だけでなく、そうした豊富な蓄積も、今後の起業に活用してほしい。企業やベンチャーキャピタルの方々にも注目してもらいたい点です。
松浦先行き不透明な時代に、会社として先端技術に対する感度を高めていくためにも、京都大学とはプログラムの枠に留まらず、いろいろな形での連携を深めていきたいです。他方、科学技術への貢献という観点では、日本の産学間の距離をより一層縮める必要があります。他大学との連携拡大も検討中ですが、京都大学のように、同じ思いを共有しながら一緒に取り組んでいくことが力になると感じています。手探りではありますが、一連の活動を通じて、新しい産学連携のあり方を模索していきたいと思っています。