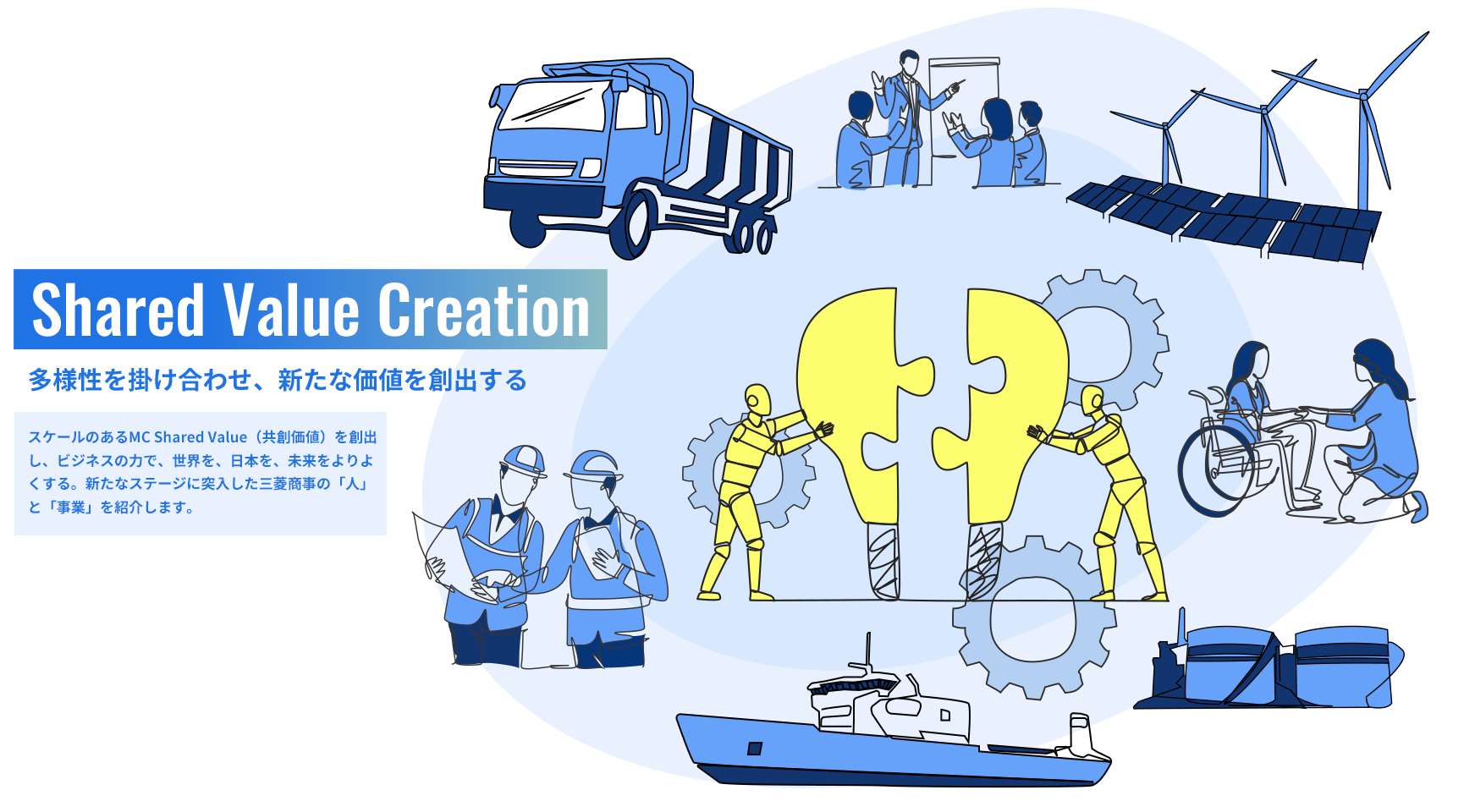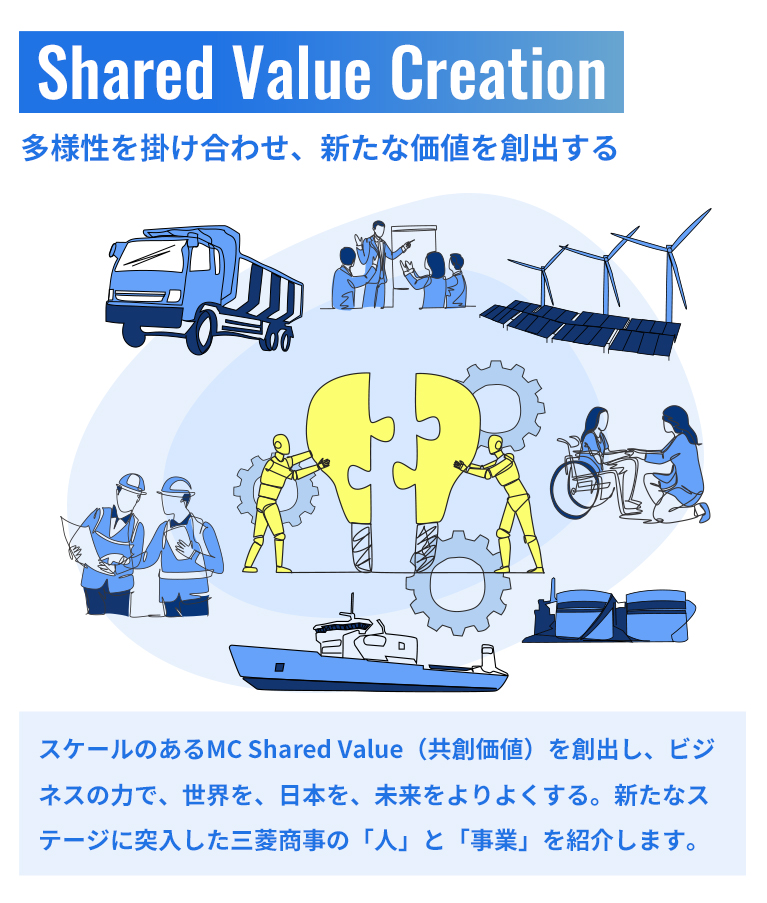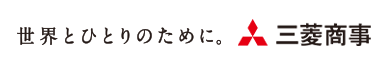国際情勢の混乱や著しい技術革新、グローバル・サプライチェーンの再構築などにより、あらゆる産業でパラダイムシフトが進みつつある現代社会。そんな中、三菱商事では、グループの総合力を生かした社会課題解決やソリューション提供を目指し、2024年度から新たな八つの営業グループに組織を改編した。本シリーズでは、新体制のもとで力強いスタートを切った各グループの現在地と見すえる将来像に迫る。
初回の主役は、不動産や都市の開発・運営から、船舶・宇宙航空機、産業機械、インフラ事業まで、多様な領域で社会インフラの課題解決・発展をリードし続けている「社会インフラグループ」。いまどんな仕事に邁進(まいしん)し、どんなやりがいを感じているのか。朝日新聞GLOBE+の関根和弘編集長が聞いた。
-

村上 一馬 氏
インフラ・船舶・宇宙航空機本部 宇宙航空機部 宇宙事業チーム
-

無量谷 優介 氏
産業機械本部 建設ソリューション部)※(株)レンタルのニッケンに出向中
-

小野 雄生 氏
国内都市開発・デジタルインフラ本部 国内都市開発部
-

熊田 のぞみ 氏
海外都市開発本部 アジア都市開発部
鎌倉・藤沢エリアをヘルスイノベーションの街に
—— 今日は、社会インフラグループの四つの本部から一人ずつお集まりいただきました。まずは、国内都市開発・デジタルインフラ本部の小野さん、担当している事業についてご紹介ください。

小野
私は神奈川県の鎌倉・藤沢エリアで、「ヘルスイノベーション」を核にした大規模な再開発案件に取り組んでいます。
鎌倉・藤沢エリアには、日本最大級の製薬・創薬の研究拠点「湘南ヘルスイノベーションパーク(通称:湘南アイパーク)」と、年間救急搬送数が2万2,000件超(2022年度)に上る日本屈指の医療機関「湘南鎌倉総合病院」があります。ここに「神奈川県」「藤沢市」「鎌倉市」が加わった5者による「ヘルスイノベーションの最先端拠点形成」を目指した取り組みが進められており、私たち三菱商事は様々な提案を行っています。
この街づくりで私たちが目指しているのは、湘南アイパークや湘南鎌倉総合病院を中心に、製薬・創薬に関わる企業や大学・研究機関、スタートアップ、ベンチャーキャピタルなどが集まり、「製薬・創薬のエコシステム*」を街全体で構築することです。
* 生物学で「生態系」の意味だが、ビジネスにおいて各企業がそれぞれの強みを生かして連携しながら、共存共栄の関係を維持することを指す。
—— 製薬・創薬の産業集積形成を目指す再開発というわけですね。鎌倉・藤沢エリアに暮らす住民にもメリットはあるのでしょうか。
小野 この再開発では、鎌倉・藤沢エリアに住む人・働く人・訪れる人の誰もが、最先端の技術を享受しながら健康で安全・安心に過ごせることを目指しています。 すでに様々な分野で実証実験を行っており、例えば、日常の通院を想定し、移動中にバイタルサイン(体温・血圧など)の計測やデジタル問診等を行える自動運転車両の走行デモなどを実施しました。 さらに、湘南鎌倉総合病院の妊産婦の方々にウェアラブルデバイス(手首など身体に装着できる小型のデジタル機器)を配布し、そこから得られる運動量や睡眠の質等のライフログを病院スタッフがモニタリングしたり、アプリを活用した健康アドバイスを産前・産後における通院時の相談や自宅での充実したケアに生かしたりする“見守り”サービスに関する実証も行いました。 地域住民に対しても、ウェアラブルデバイスで日常のライフログを活用し、運動・睡眠・栄養に関する健康増進プログラムを提供することで、日頃から健康意識を高めてもらうとともに、将来的には病気にかかった時のデータ活用なども視野に入れています。 この街で暮らすだけで健康になれる……とまでは言えませんが(笑)、将来的にはそんな「ヘルスイノベーション」を実現できる街を目指していきたいと考えています。
ベトナムの住宅事情に商機 理想の家を届けたい
—— 同じ不動産分野の中でも、アジアや北米を中心とした海外で不動産や都市の開発・運営を担っているのが、海外都市開発本部ですね。

熊田 はい、その通りです。私は、アジア都市開発部でベトナム事業を担当しています。経済成長著しいベトナムにおいて、5年ほど前から首都のハノイ・商業の中心であるホーチミンの二大都市で大規模不動産開発事業を推進しています。 現在、私が担当している事業は主に二つ。一つは、経済発展と人口増加の一方で優良な住宅が圧倒的に不足しているベトナムで、優良な分譲住宅を提供する不動産開発事業。そしてもう一つが、不動産関連市場におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)事業です。
—— 不動産におけるDX事業とは、どのようなものですか。
熊田 平たく言えば、ベトナムにおける「インテリアデザインに関する悩み」を解決するサービスです。日本では、家を購入したらあとは家具をそろえれば住むことができますよね。ところがベトナムでは多くの場合、家を購入した時点では中は“空っぽ”の状態。キッチンやお風呂などの内装工事は、自分で手配をするのが一般的です。 つまり、自分で町の工務店を探し、自分で予算を決め、自分で仕上がりイメージを考える。さらに工務店と打ち合わせをして要望を伝え、進捗(しんちょく)・品質・予算管理まで自分で担う必要があるということ。これって一般の消費者には、かなり大変な作業ですよね。しかも苦労した末、理想の家が出来上がればいいのですが、実際は「思い描いていた仕上がりと全く違う」「納期が大幅に遅れた」「予算もオーバー」などというケースがとても多いのです。 せっかく夢のマイホームを手に入れたと思ったのに、これではもったいないと考え立ち上げたのが、私が担当するDX事業です。品質の担保された工務店をあらかじめ選定して紹介したり、内装のデザインをテンプレート化してオンラインで提案し、その中から自分でカスタマイズできるようなサービスを考案しました。試験運用を通して現地のデベロッパーや販売代理店と少しずつ関係性を構築したかいあって、ようやく現地の大手デベロッパーから協業依頼を受けるまでに至っています。これから徐々にサービス提供範囲を拡大し、数年以内をめどにベトナム全土でサービスを開始することを目指しています。一人でも多くの方が、自分の理想の家で幸せに暮らせる日が来るよう、引き続き取り組みを進めていきます。

——お二人のお話を伺っていると、不動産分野といっても、建物を建てるだけでなく、街づくりや住民向けのサービス開発など、実に幅広い領域に携わっていることに驚かされます。
熊田 そうですね。もちろん建物の建設そのものも担っていますが、我々三菱商事がデベロッパーさんと大きく違うのは、建物という「点」だけではなく、「面」で開発ができるところだと思います。建物や都市というプラットフォームを開発し、そこにエネルギーやモビリティ、デジタルサービスといった各種コンテンツを自社のネットワークの中から提供することができる。それによって、不動産や都市のバリューアップにつなげられる、というわけです。 小野 鎌倉・藤沢エリアの都市開発・都市運営事業は、街のコンセプトを考え、開発プランを検討するところから一つずつ、関係者の方々と協議しながら進めています。関係者が多いぶん調整が大変なこともありますが、まさに「面」で開発・運営することによって、地域の課題や産業構造の課題の解決に貢献できる。さらに、街の持続的な価値向上にもつながっていく。とても面白く、やりがいを感じています。
アナログな建設業界 レンタル事業のDXで風穴を
——続く産業機械本部は、電力・石油・ガスなどの産業インフラ、空港・鉄道システムなどの社会インフラ、さらに工作機械等の各種産業設備や大型農業機械の販売事業など、実に多様な事業がありますね。今回は、建設ソリューション事業について、ご紹介をお願いします。

無量谷 私はいま、産業機械本部建設ソリューション部から、株式会社レンタルのニッケン(以下、ニッケン)に出向しています。ニッケンは三菱商事の事業会社で、主に土木・建築・産業関連機械を中心とした機器・設備をレンタルする会社です。約250の拠点があり、日本全国で事業を展開しています。 一般の方にはあまり知られていないかもしれませんが、実は建設現場で使用されるほぼ全てのものは、レンタル品で成り立っています。ショベルカーやダンプカーなどの大型の建設機械はもちろん、夜間工事に使う照明機、さらに三角コーンや安全ロープのような小さなものまで、ニッケンが取り扱っている商品は、約4,700種類・約120万点にも上ります。ゼネコンや建設会社に「必要な時に・必要なものを・必要な分だけ」貸し出すというビジネスです。
—— 生産性向上のために、業務のデジタル化を進めているそうですね。
無量谷 建設業界=トラディショナルな業界、というイメージはなんとなく抱いていましたが、実際にその様子を目の当たりにした時は驚きました。数年前まで建機レンタルの注文は、電話やFAXが当たり前。それゆえ、「FAXの字が汚くて発注内容が読めない」「日中は電話対応で忙しい」、お客さんの側も「夜間に注文したくても終業後で人がつかまらない」「レンタル商品の管理が行き届かず、重複して注文してしまった」など、アナログゆえの非効率的なやり取りが日常茶飯事でした。 そこで、業務の効率化を図るべく、2021年に開発・リリースしたのが「オンラインレンタル」サービスです。お客さんは24時間いつでもスマートフォンやタブレット、パソコンから納品・返却依頼ができるようになったうえ、現場にある機材の種類・数量をリアルタイムで確認・共有できるため稼働管理もスムーズになりました。さらにいまは、レンタルする機械にGPSを取り付けることで、広大な現場でも「どこでどの機械が稼働しているのか」が瞬時に把握できる仕組みを導入し、一部でサービスを展開しています。 また2024年4月からは、ニッケンに「データ経営推進室」を立ち上げ、ビッグデータの活用によってより合理的な意思決定ができるよう、取り組みを進めています。例えば、お客さんからの受注後、どこにあるどの商品をどんなルートで届けるのが最も効率的であるかをAI(人工知能)が判断できるようになれば、物流の無駄も省くことができます。需要予測をもとに、レンタル商品の最適な配置や購入ができれば、建機の回転数を最大にし、機会損失を防ぐことができます。加えて、今後は新たなビジネスモデル構築にも挑戦していくつもりです。

—— 出向者という立場で会社を改革していくことに、やりにくさなどは感じませんか。
無量谷 それは感じないですね。私はニッケンに来て4年が経ちますが、仲間と信頼関係を築いていけるかどうかは、もとの所属うんぬんではなく、「本気で建設業界や建機レンタル業界を良くしようと思っているか」「目の前のビジネスを愛しているか」にかかっていると思います。 もちろん、オンラインレンタルの導入などのように、これまで現場の皆さんが慣れ親しんできたやり方を大きく変えるという際には、一定の反対は出るものです。それでも、変えることの将来的な意義を理解してもらえるようしっかりと話し合う。必要とあらばニッケン、三菱商事関係なくとことん議論する。そうした姿勢・行動が周りに伝われば、自然といい関係性ができていくものだと思います。
注目の宇宙ビジネス 三菱商事が参画する意味は
—— インフラ・船舶・宇宙航空機本部には、宇宙事業チームがあるんですね。三菱商事が宇宙ビジネスまで担っているとは、驚きました。

村上 たしかに「宇宙×総合商社」という組み合わせは、少し理解されにくいかもしれないですね。まず前提として、宇宙産業はいま、非常に大きな変革の真っただ中にあります。革新的な技術開発が進んでいることに加え、宇宙はかつての「国家」主導の事業から、「民間」主導のビジネスの場へと変わりつつあります。すでに国内外でスタートアップの立ち上げや異業種からの参入が相次いでおり、業界やビジネスモデルは大きく変わりつつあるのです。 そんな中、私自身は三菱商事の宇宙事業チームで、主に二つの新規事業開発をリードしています。一つが「宇宙ステーション事業」です。現在運用中の国際宇宙ステーション(以下、ISS)の退役に伴い(2030年頃を予定)、その後継基地の開発として米NASAは民間企業が主導する商業宇宙ステーションプログラム(以下、CLD Program)を進めており、CLD Programにおける有力企業の一つが、2024年1月に米宇宙関連企業Voyager Space社と仏Airbus社によって設立されたStarlab Space社(以下、スターラブ)です。2024年4月、三菱商事は両社に次ぐ3社目の戦略パートナーとして出資参画し、ともに運営にあたっています。2024年5月にはカナダ宇宙関連企業のMDA Space社も参画し、2026年のNASAによる商業宇宙ステーション事業者選定に向け活動中です。
—— スターラブとの事業で、三菱商事は具体的にどんな役割を担うのでしょうか。
村上 三菱商事の役割は、宇宙関連技術を提供する企業や、宇宙空間を利用したいと考えている産官学の需要者とともに、新たなビジネスモデルの構築、需要の創出、宇宙利用の環境整備など、宇宙における事業開発を進めることです。 地球の約400キロ上空を飛行するISSの中は、「微小重力環境」という地上の約100万分の1の重力の世界です。この微小重力環境を利用した実験・研究が、生命の謎の解明や新たな素材の開発、創薬研究、半導体結晶の生成など、様々な産業のイノベーションにつながると期待されています。 そこで私たちは、需要の創出、つまり国内外の企業やアカデミア等に参画を促すとともに、サプライチェーンやバリューチェーンを再定義していきたいと考えています。そのような形で事業開発をリードし、スターラブとしての事業拡大はもちろん、日本の宇宙産業市場を拡大していく役割を担うべく、日々挑戦しています。

—— 宇宙ごみの除去にも取り組んでいるそうですね。
村上 その通りです。私が取り組んでいる二つ目の事業が、宇宙活動を支える「軌道上サービス事業」です。人工衛星をはじめ宇宙空間にあるアセット(資産)は増え続けており、スペースデブリと呼ばれる宇宙ごみの存在は深刻な問題となっています。衛星に衝突すれば社会インフラの途絶にもつながりかねません。 そこで三菱商事は2023年に、宇宙ごみ除去の事業化を目指す株式会社アストロスケールホールディングスに出資し、宇宙ごみ除去に加え、観測・点検などにより人工衛星の寿命延長や宇宙ごみの発生抑制にも寄与する、総合的な「軌道上サービス」の事業検討を進めています。宇宙ビジネスの持続可能性を守るために、宇宙活動を支える軌道上サービスは不可欠だと考えています。
日本のプレゼンスを高めていくために
—— お話を伺っていると、時に三菱商事のビジネスという枠を超えて、「日本のプレゼンス向上のため」「日本の国力のため」という強い思いが感じられたことが印象的でした。

村上 実はまさにそれが、私が宇宙産業に身を置きたいと思った理由なんです。私はキャリア入社で、以前は別の商社で発電所の建設プロジェクトを担当したり、通信事業会社で次世代衛星通信の新規事業開発を行ったりしてきました。それぞれ大変やりがいがありましたが、「もっと日本という国に貢献したい」「この国を経済的により豊かにしていきたい」と考えた時、新たな市場として発展の余地が大きいと思えたのが、日本の宇宙産業でした。 実際、ISSでの長年にわたる日本の実績は非常に高く、現時点で日本のプレゼンスは高いといえるでしょう。ただ、熾烈(しれつ)な国際競争が始まっているいま、それを維持・拡大していくためには、国内外での積極的な民間企業主導の事業開発が不可欠です。日本の宇宙産業のために、今後も全力で取り組んでいくつもりです。 小野 その点は、私も強い思いがあります。日本はもともと世界有数の製薬・創薬国でした。ところが近年、バイオ医薬品が革新的医薬品の主流となったことで、日本の製薬・創薬産業のプレゼンスの低下が懸念されています。 世界の新薬開発はいま、大学などの「アカデミア」が基礎研究を行い、それを「スタートアップ」が事業化して成長させ、最終的にM&A(企業合併・買収)やIPO(新規株式公開)によって「製薬会社」から市場に出ていくというプロセスが確立しています。一方、日本は、基礎研究においては世界に通用する力があるにもかかわらず、それを事業化するスタートアップが育っておらず、資金調達の絶対額が小さいという課題があります。 そこで私たちは、研究施設の整備、研究機関や金融機関の誘致などの開発を一体的に進めることで、製薬・創薬のエコシステムを街全体で構築し、この課題解決に貢献できたらと考えています。我々のモデルケースとなるのは、半世紀を超える歴史を持つ、英ケンブリッジサイエンスパーク。視察に訪れた際は、「いかにして地域全体でエコシステムを構築するか」や「行政との関わり方」について、大いに学ばせてもらいました。日本の製薬・創薬業界のために、今後も三菱商事としてできることを模索していきます。
- 次回は、社会インフラグループ座談会の後編をご紹介します。