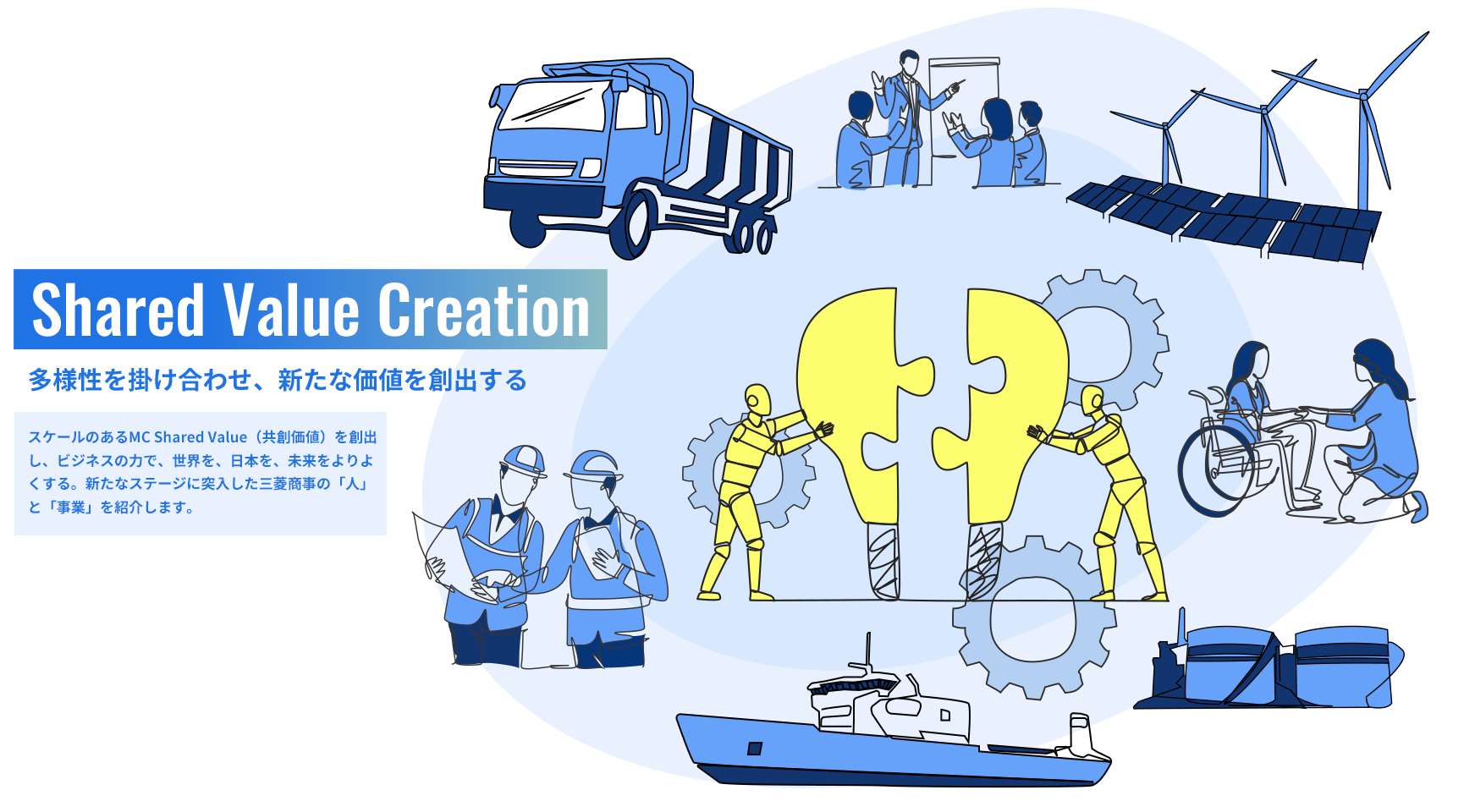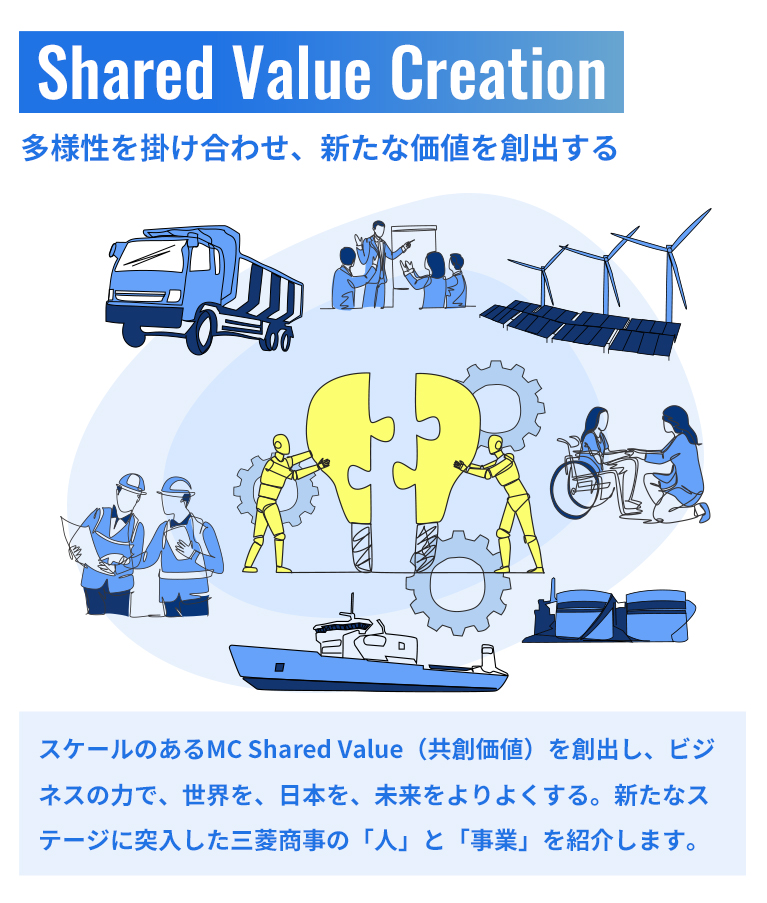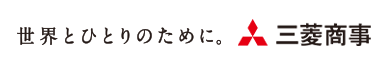時に営業グループの伴走者として、時に経営者の“助手席”に座る存在として、三菱商事の事業運営を支える「コーポレートスタッフ部門」。座談会の後半では、これまでのキャリアパスや仕事のやりがい、今後への思いを語り合った。(聞き手:朝日新聞GLOBE+編集長・関根和弘)
-

リム チョンキョ 氏
グローバル総括部
アジア・大洋州室 -

安宅 貴弘 氏
ITサービス部
ITインフラチーム -

畑中 美紗子 氏
事業投資総括部
投資総括チーム
統括マネージャー
※所属は2025年1月取材時
※本文は敬称略
[聞き手] 関根 和弘(朝日新聞GLOBE+編集長)
海外拠点からのキャリア入社 後進の良きモデルになれたら
—— これまで、皆さんがいま担当されているお仕事について伺いました(※前編参照)。続いて、これまでどんなキャリアを歩んできたのか、グローバル総括部のリムさんから教えてください。

リム 私は韓国で生まれ、高校卒業まで日本で育ちました。大学から韓国に戻り、2010年に三菱商事の海外拠点の一つである韓国三菱商事に入社。財務経理を担当しました。 2013年からは、希望していた東京本社への出向がかない、金属資源グループの管理部で初めて連結会計を扱うことに。それまで数字を報告していた立場から数字を受け取る側になったことで、「どういう情報が、どんな理由で必要なのか」がより明確に理解できるようになりました。3年後に韓国三菱に帰任してからも、東京本社で学んだこの視点は大いに役立ちました。 2019年からは2度目の出向でシンガポールへ。アジア域内の事業会社を広く支援する組織にいたので、2週間に1度ぐらいのペースで、ミャンマーやバングラデシュなど各地を飛び回りました。市場開発から社内規程の作成、イベントの支援まで、何でもやりました。おかげでアジア各国への理解が深まり、「この国ならこんな風に事業が進んでいくだろう」といったことが肌感覚で分かるようになったのは、非常に大きな収穫でした。 コロナ禍においては、東京本社の危機管理室とも連携しながらアジア域内の危機管理・避難支援業務に従事しました。その後、シンガポールから帰任。2024年4月から「キャリア採用」という形で東京本社に採用され、グローバル総括部で働いています。
—— 韓国から東京、シンガポール、そしてアジア各国と、まさに商社らしいグローバルな活躍ですね。
リム グローバル総括部は海外拠点と相対する立場にあるので、海外駐在に出る確率は高いですね。世界を舞台に働きたいという人にとっては、ぴったりの部署の一つだと思います。 当部にも、韓国のほか、中国やエジプト、アフリカや欧米など、多様なバックグラウンドの社員がいます。東京本社全体となるとその対象は全世界に広がります。インテリジェンス(※前編参照)も市場開発も人事戦略も、多面的な視点・価値観を持った組織を作っていくことが、今後はますます大事になっていくと思っています。
—— リムさんのように、海外拠点から東京本社にキャリア入社するケースは多いんですか?
リム コーポレートスタッフ部門に関しては、海外拠点からのキャリア入社はまだ多くありません。私がここでしっかりと成果を出していくことが、国籍の違う社員や、海外拠点からのキャリア入社を希望する社員の“道しるべ”になると思っています。後に続く人たちのためにも、そして、三菱商事がバックグラウンドを問わず活躍できる会社であることを内外に示すためにも、さらに成長していきたいですね。
駐在先で直面した価値観の違い どう乗り越えたか
—— 畑中さんは、「リスク管理のスペシャリスト」としてキャリアを重ねてこられたようですね。

畑中 キャリアのスタートは、三菱商事フィナンシャルサービスという経理の事業会社の審査部門で、取引先から債権を回収する「信用リスク管理」という仕事でした。その後、食品産業グループの管理部で予算・決算や事業投資管理を担当しました。食品の流通を担う事業会社・三菱食品に出向した際は、会社全体のリスクを一元管理する「ERM(エンタープライズ・リスクマネジメント)」を構築するプロジェクトにも携わりました。 その後、産休・育休を経て、2018年にロンドンに赴任しました。再生可能エネルギーへの投資を手がけているDiamond Generating Europeという会社へ、リスクマネジャーとしての出向です。投融資委員会の立ち上げ・運営やリスク規程の策定・整備などを担当しました。 2020年、今度はオランダへ赴任。欧州で総合エネルギー事業を展開するEnecoという会社を三菱商事などが買収したのを機に、現地の「内部統制整備」を支援することになりました。信頼性の高い決算・財務報告を行うための枠組みを整備するプロジェクトでした。信用リスクや事業投資リスクに比べ、こちらは会社内部のリスクに対応するものですが、広い意味でリスク管理の一部と言えます。苦労も多かったのですが何とかやり遂げ、2023年夏に帰国しました。事業投資総括部に配属され、いまは統括マネージャーとして四つの営業グループの投資案件審査を担当しています。
—— 海外での仕事では、文化や価値観の違いに戸惑うことも多かったのではないでしょうか。
畑中 例えば、オランダで直面したのは、リスクやルールに対する考え方の違いです。日本では、一般的に「ルールベース(Rule-based)」といわれる、ルールを守ることを重んじる考え方があります。 もしもルールが実態に合っていなければ、ルール自体を見直していくという考え方です。対するオランダは「リスクベース(Risk-based)」の考え方が強いように思います。そもそもこのルールはどういうリスクに対応するために存在するのか、とリスクの方からものを考える傾向にあります。当初はこの違いを認識していなかったので、話がかみ合わないことがあり、結構苦労しました。 一般的なところでは、例えば「ものの言い方」もかなり違います。日本でよく使う婉曲(えんきょく)的な言い回しをしたら、「あなたが何を言いたいのか分からない」と言われてしまったこともあります(笑)。オランダ人の多くは「反対・賛成」「好き・嫌い」をものすごく率直に表明するんです。 それから「議論の仕方」も違います。互いの意見が対立するとき、日本的な感覚だと「落としどころ」を見つけるというか、譲歩できるラインを探ることってありますよね。ところがオランダでは、「あなたは自分の意見に自信がないのか?」と不思議がられてしまいました。 オランダでは議論をし尽くしたうえで、はっきりと勝敗を決めることを好む傾向にあるようです。ちなみに、議論の場で激しくやり合っても人としての関係性は何ら変わらない。そんなスタンスはサッパリしていて気持ちがいいものでした 。
—— 異文化ゆえの行き違いや誤解は、膨大にあるでしょうね。どう乗り越えましたか。
畑中 何か特別なことをしたわけではなく、一つひとつ丹念に誠実に話し合いを重ねることで、徐々に信頼関係を築いていったという感じでしょうか。自分の“全部”で相手に向き合っている感覚があって、人間力というものを鍛えられたように思いますし、刺激的で楽しかったです。当時の同僚たちは、いまでも出張などで来日する機会があると声をかけてくれて、食事に出かけたりします。 コミュニケーションの方法という点では、相手にすべて合わせるわけでも、自分のやり方に固執するわけでもない、「自分らしく振舞える立ち位置」を選びとって対処するスキルが身についたように思います。いまの職場でも難しい議論の局面はありますが、こうして多様なバックグラウンドの人たちとコミュニケーションをとった経験も、大いに役立っていると感じます。
—— ロンドンやオランダへの駐在には、お子さんも連れてご家族で行かれたそうですね。
畑中 2人目の産休・育休復帰と同時に、夫と5歳・0歳の子どもと一緒にロンドンへ赴任しました。海外駐在をしたいという希望を伝え、会社とは復帰前の早いタイミングから綿密に相談できました。夫は大学院に通いながら、家事・育児の多くを引き受けてくれました。会社や家族、周囲の方々など、多くの人の助けと支えがあって実現した駐在でした。 日本では、出産・育児で、女性が、望む・望まないにかかわらずキャリアをスローダウンすることも結構あると思います。「こういうパターンもあるんだな」と参考にしてもらえたらうれしいです。それから個人的な願いとしては、娘に「将来、ママみたいな働き方をしたい」と思ってもらえるようになりたいです。
研究者志望から転身 ITビジネスに挑んだ理由
—— 安宅さんは、ITサービス部を志望して三菱商事に入社したと伺いました。

安宅 私は大学院までエネルギー領域の研究をしており、将来は研究者になるつもりでした。ただ、企業でのインターンシップなどを経験し、「優れた技術の社会実装を通じて社会課題を解決したい」と強く思うようになったんです。そこから研究よりもビジネスへの関心が強くなりました。 当時は、AIやクラウドコンピューティングが急速に発展し始めた時期だったため、「ITやDXの先進技術を活用したビジネスに携わりたい」と考えるようになり、2016年に三菱商事に入社しました。
—— 入社後は、早く現場に出ることを望まれたそうですね。
安宅 その通りです。ITサービス部では、三菱商事のバックオフィスの強化のほか、事業会社のIT・DX推進を支援する取り組みに携わりました。電力小売り事業や建機レンタル事業、そして「ローソン」などです。その後、現場に身を置いて仕事がしてみたいという希望が叶い、2020年からローソンへ出向。「AI.CO(AI Customized Order/AI Consultant)」の開発(※前編参照)に携わることになりました。 「AI.CO」の開発では、「現場の人の話を丁寧に聞く」ことを徹底しました。というのも、業務のフローやプロセスを把握していなければ、使いやすいシステムを作ることはできないからです。とくに現場にとって“当たり前”の判断や業務内容ほど、言語化されにくい傾向にあります。これを丁寧に拾えるかどうかが「システムの使い勝手」を大きく左右します。 ローソンの営業部やスーパーバイザーの皆さんはもちろん、店舗のオーナーの方々に幾度もヒアリングさせていただいたことが、「AI.CO」開発の大きな力になりました。
—— ローソンで得たことを、今後の業務にどう生かしていきますか。
安宅 ローソンでの経験を通して、「店舗のために」「お客様のために」という現場ファーストの意識がより一層高まりました。また、24時間365日、正常稼働することの重要性もあらためて実感しました。 安定した企業運営・グループ経営を支えるべく、今後も全社のITマネジメントやITインフラの整備・システム開発に注力していきます。そしてまた、海外も含め新たな事業領域の現場で、営業グループの皆さんに伴走しながら、社会課題解決に寄与できたらと思っています。
多彩・多才な人材のミックスが組織のプラスに
—— 皆さんのキャリアの変遷を伺って、営業グループへの社内出向や、事業会社への出向が多いことに驚きました。

畑中 そうですね。本社のコーポレートスタッフ部門と営業グループや事業会社を行き来するキャリアパスはとても多いです。全社を俯瞰(ふかん)した経営的な目線での仕事と、特定の事業領域内における仕事を繰り返し経験することで、コーポレートスタッフとしての知見がより深まっていくと思っています。 私自身も再エネの会社に出向していた経験があるので、これらの産業におけるリスク管理に関する知識・経験は、ほかの領域より持っているかなと思います。 安宅 私もローソンに出向したことにより、営業現場で働く皆さんの考えを理解し、それを生かしたシステム開発ができるようになりました。多角的な視点を持つことができるという意味でも、こうした人材の行き来は意義があると思います。
—— 逆に、営業グループの人がコーポレートスタッフ部門に来ることもあるのですか。
畑中 はい。私の所属している事業投資総括部はそれが顕著で、長年コーポレートスタッフ部門にいるメンバーと、営業グループからの社内出向メンバーの混成チームで業務にあたっています。営業グループのメンバーが持つ各事業領域の深い専門知識や豊富な経験は、リスク分析を進めるうえで非常にプラスになります。また営業グループに戻った後は、そこでリスク管理の考え方を浸透させる役割も果たしてくれます。 リム いまグローバル総括部にいる私の上司も、元々営業グループの所属でした。やはり、長くコーポレートスタッフ部門にいる我々にはない視点を持っており、学びや気づきがとても多いです。一方で、その上司いわく「グローバル総括部で全世界を見渡す立場になったことで、私自身の知見は非常に広がった。かつ、経営陣との距離が近いので、三菱商事の全社経営に対する理解度・解像度が格段に上がった」と。様々なメリットのある人材の循環は、今後もますます進めるべきだと思います。

—— 三菱商事は、中期経営戦略2024で「イキイキ・ワクワク、活気あふれる人材と組織」を掲げています。日頃の働きやすさや様々な制度についてはいかがですか。
安宅
人材育成に熱心な会社だな、と思っています。私は新卒の頃、ITの素養はほとんどありませんでしたが、入社後にIT・デジタルの基礎をみっちり学べる研修があって、非常に助かりました。その後も様々なサポートがあり、私はAIのエンジニア向けの資格を取得。そのスキルを「AI.CO」のプロジェクトの際にも生かすことができました。
また、人事担当や部の上司とは定期的に面談があり、個々の希望や志向にできる限り沿うよう、一緒にキャリアを考えてくれます。私自身はまだ活用したことがないのですが、「Career Choice」制度※で希望する組織への異動ができるチャンスもあり、社員の意欲を大事にしてくれているなと感じます。
※「Career Choice」制度:手上げ制異動制度。個人のキャリア希望、今後伸ばしていきたい能力・資質などを踏まえ、自らが挑戦したい組織への異動を後押しする制度。自律的キャリアを促す制度として、ほかに、社内複業を通じたスキル習得・成長機会を提供する「Dual Career」制度、国内外の大学・大学院への進学を通じた学び直しに取り組める「サバティカル休職」制度などもある。
リム
企業風土という点では、役職などに関係なく自由にものを言える風通しの良さは日々感じています。制度に関しては、海外駐在時の手厚い手当・サポートがとてもありがたかったです。おかげで海外生活の不安や不便をそれほど感じることなく、仕事に集中でき、現地にも早くなじむことができました。
畑中
働く時間を柔軟に配分できる「フレックスタイム制勤務」が導入されており、私も活用しています。いま小1と小6の子どもがいるので「学校行事の数時間だけ仕事を抜けたい」といったケースでは、とてもありがたいですね。育児に限らず、介護やそのほかの色々な事情がある人にとって、大きな助けになります。「配偶者転勤同行再雇用制度」※を活用している同僚もいます。パートナーとのキャリアの共存を後押ししてくれる良い制度です。
※配偶者転勤同行再雇用制度:社員が配偶者の国内外転勤に同行するために退職する場合、一定条件のもとで再雇用をする制度。
「どこでも・何でもできる」可能性は無限大
—— 最後に、コーポレートスタッフ部門で働く醍醐(だいご)味や面白さをあらためてお聞かせください。

安宅
コーポレートスタッフ部門の専門性・機能は、事業領域が違っても共通する部分があるので、業界・業種を越境して仕事ができます。とくに、三菱商事の事業のフィールドは非常に幅広いので、一層その面白さを享受できるのだと実感しています。「三菱商事のコーポレートスタッフ部門ならではの醍醐味」を感じながら、今後もさらに精進していきたいと思います。
リム
「やろうと思えば何でもできる」という点でしょうか。例えばグローバル総括部なら、財経的な業務や人事的な業務もできますし、市場・事業開発といった営業的な動きもできます。自分のやる気と能力さえあれば、どんな国・地域でもどんなビジネスでもできる。それが醍醐味ですね。
畑中
「学び」と「刺激」が非常に多い環境であるということです。三菱商事は関わっている産業の接地面積が広いですから、多種多様な案件に接することができます。さらにその過程で、幅広い事業分野の人たちとコミュニケーションをとる機会があります。異なる知見や専門性、価値観、感性を持っている人たちと日々接することができるのは、刺激的であり純粋に楽しいなと感じます。
さらに自分の専門性を磨くことで、それを武器にして、どこの国・地域、どこの事業領域へも羽ばたいていけます。この可能性の大きさは、コーポレートスタッフ部門の仕事の大きな魅力だと思っています。
* グループ名・部門名は、2025年3月現在の組織に該当する名称で表記しています