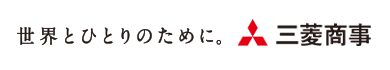Steps for the BETTER FUTURE:「DX」がもたらす新しい社会への決定的な変化とは
様々なビジネスの現場で必要性が叫ばれている「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」。その本質とは、推進に必要なこととは。
東京大学未来ビジョン研究センター客員教授の西山圭太氏と、三菱商事のDX戦略を担うMC Digitalの社員が語り合った(第2回)。

座談会参加者
西山 圭太氏(東京大学未来ビジョン研究センター客員教授。株式会社経営共創基盤シニア・エグゼクティブ・フェロー)1985年、東京大学卒業後、旧通商産業省入省。92年、英オックスフォード大学哲学・政治学・経済学コース修了。株式会社産業革新機構専務執行役員や東京電力ホールディングス株式会社取締役、経済産業省商務情報政策局長などを歴任。日本の経済・産業システムの第一線で活躍し、2020年退官。著書に『DXの思考法』(文藝春秋)/久保長 礼氏(MC Digital Chief Technology Officer)/中田 勇介氏(MC Digital データサイエンティスト)/野村 実広氏(三菱商事 兼 MC Digital プロジェクトマネージャー)
- —— そもそもDXの核心とは何であり、なぜ今DXが求められているとお考えですか。
-
西山今、私たちはデジタルやAIによって「決定的な変化が起きている時代」に生きています。個人がスマートフォンで目的地までの経路を検索するとき、エンジニアに頼まなくてもソフトウェアがユーザーに直接回答するようになりました。従来は個人や組織が担ってきたことをソフトウェアが代替するようになったのです。ビジネスはもちろん、社会や政府のあり方をも変えていく、これまで人類が経験したことのない、新しい社会への移行が起きていると感じています。
- —— DXの進展は、日本の企業やビジネスのあり方にどんな影響を及ぼすと思いますか。
-
西山これまで日本の組織の多くは、事業部門ごとや省庁ごとといった「タテ割り」の行動様式でビジネスやサービスを提供していました。ところが、今日のグローバル経済を突き動かしているデジタル化のロジックは、「ヨコ割り」です。身近な例でいえば、便利なオンライン会議のツールが既に世の中にあるなら組織固有のツールは不要になるし、上司は部下に調べ物を命じなくても必要なデータやコンテンツに自分でアクセスできるわけです。このように「ヨコ割り」のソフトウェアによってソリューションを得られるようになったわけですから、ビジネスや組織の「タテ割り」の行動様式は変わっていかねばなりません。タテ割りのやり方や思考法に慣れ親しんできた日本にとって、この変革は非常に大きなチャレンジになると思います。
- —— そのDX戦略の担い手として、三菱商事はMC Digitalを3年前に設立しましたね。
-
久保長三菱商事グループは、川上から川下まで多様な業種・企業と広く深く関わっています。その三菱商事が持つノウハウを活用してDXを内製化するために設立されたMC Digitalは、グループ外の企業も含め、様々な業界のDX実現を目指して取り組んでいます。個々の企業ではなくサプライチェーン全体の最適化が図れることや、成功事例を複数の業種へ横展開できることは、MC Digitalならではの強みだと思っています。
西山僕がDX実装のために重視していることの一つが、「そもそも物流とは」、「そもそも人事とは何をするのか」といった、ビジネスが提供する価値とその方法の骨格を洗い出す「抽象化」です。スムーズなデジタル化のための「翻訳」といってもいいでしょう。MC Digitalは、三菱商事が商社として多様なビジネスで得たノウハウを最大限生かしながら、ビジネスドメインとデジタル化とを結び付ける「抽象化」を非常にうまくやられているように見えます。データサイエンティストとして実感することはありますか。
中田今、様々な業界で、生産管理や需要予測、物流リソースの最適化などの問題が生じています。これらは一見、異なる業界の異なる課題に見えますが、ある程度のレベルに「抽象化」して考えると、問題の性質に共通点が見えてきて、解決につながることがあります。
野村「抽象化」の具体例として、ソフトウェアは、「(和服の)着物」のようだと思いました。型が決まっている「洋服」とは異なり、「着物」は着る方の身体に沿って成形できます。つまり「着物」は、身体を包み、暖や美を提供するという、衣服としての本質的な用途を、ユーザーに合わせ汎用的に提供できていると感じるからです。
西山なるほど。僕は「AIの気持ちになって考える」といういい方もするんですが、例えば化学プラントのAIは「俺は原油からエチレンを作っている」「次はエチレンからフィルムを作ろう」なんて考えず、純粋にデータとソフトウェアを駆使して化学変化のプロセスを制御していますよね。抽象化することで「業種」の捉え方も今後は変わっていくと思います。
野村私たちはDXの実装に向けて、現場に足を運んだり、担当者と話をしたりする機会も多いのですが、現場の方にとっては「当たり前で言葉にするまでもない」といった部分に実は課題が隠れていることもあります。そのため、小さなこともありのままにお話しいただき、そこから課題を照らし出し、常識や前提にとらわれずに解決策を提示するよう努めています。
久保長「そもそも論」を問うことは、非常に重要だと思います。企業や業界が自らを抽象化したゴールを設定し、そこに向けて最適化してこそ、私たちがつくるソフトウェアにも大きな価値が生まれると考えています。
中田企業のゴール達成には、CTO(Chief Technology Officer)の役割が重要です。テクノロジーに精通した人材が、組織や現場をリードしていく必要があるからです。
西山現場の課題を「翻訳」し、さらにヨコ割りの視点でデジタルのソリューションにも「翻訳」しているといえますね。MC Digitalの取り組みによって、今後さらなる創造性が発揮され、新たな価値が生み出されていくことを期待しています。