統合報告書2022PDF一覧
目次
-
【イントロダクション】 (PDF:3.3MB)
目次/編集方針/企業理念/社長メッセージ (PDF:1.9MB)/中期経営戦略2024/特集 未来創造(新産業創出/地域創生)/中期経営戦略2021振り返り
-
【価値創造ストーリー】 (PDF:4.1MB)
価値創造の軌跡/価値創造のプロセス/6つの資本/Focus 人的資本 - 価値創出の源泉/マテリアリティ/Focus 気候変動 - EX戦略の前提となるマテリアリティ/CAOメッセージ/CFOメッセージ
-
【営業グループの価値創造】 (PDF:3.4MB)
営業グループ At a Glance/ビジネスモデル ✕ 事業
-
【サステナブルな価値創造を支える取り組み・体制】 (PDF:3.7MB)
サステナビリティ推進体制/リスクマネジメント/コーポレート・ガバナンス
-
【データセクション】 (PDF:2.6MB)
取締役・監査役/執行役員/株主情報/組織体制/グローバルネットワーク(国・地域)/13カ国におけるリスクマネー残高状況/財務ハイライト/主要な関係会社等の持分損益/ESG情報/会社情報



CAOメッセージ
再定義したマテリアリティに
立脚した取り組みを実施し、
企業価値の中長期的な維持・
向上を実現していきます
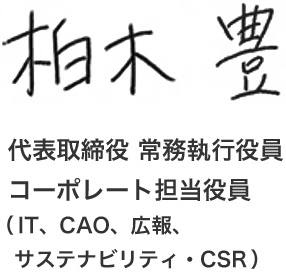
気候変動や人権問題をはじめ、解決すべき社会課題が多様化・複雑化する中、企業としても本業を通じ、その解決に取り組むことが必要不可欠となっています。激しい外部環境の変化に伴い、政策・法規制の整備や国際的なイニシアチブの創設も進み、民間資金の流れ、投資家の行動様式も大きく変容してきています。具体的には、気候変動への対応はもちろんのこと、変化の速い事業環境に対応可能なガバナンス体制が構築されているか、競争力の維持・向上の担い手たる従業員の育成がなされているかといった、非財務に関する取り組みが企業価値に大きく影響する時代になってきており、サステナビリティへの取り組みが不十分な場合は企業にとって不利益となり、逆に積極的な推進は中長期的な成長に不可欠であると考えています。加えて、企業が事業活動を行う上で、その存在が前提条件となっている生態系サービスや自然環境が損なわれた場合、直接的には自社のオペレーションに、間接的にはサプライチェーンに影響が生じるなど、企業にとって大きなリスクとなります。従って、社会課題の解決に取り組むことは、企業にとって、リスクマネジメントであると同時に、ビジネスチャンスの追求でもあると捉えています。
マテリアリティに立脚した取り組み(経営)
当社は、企業理念である「三綱領」に基づき、2010年の中経2012で「継続的企業価値の創出」、2016年の中経2018で「三価値同時実現」を掲げ、サステナビリティへの取り組みを進めてきました。また、同じく2016年には、当社の「持続可能な成長のために特に対処すべき重要課題」として「サステナビリティ重要課題」の特定を行いました。一方、「サステナビリティ重要課題」の策定から6年が経過し、気候変動対策をはじめとして、企業に対する期待は高まるとともに、解決すべき社会課題も変化しています。本年5月に公表した中期経営戦略2024(以下、中経2024)では、そのような社会課題の解決を通じて継続的に生み出される、スケールのあるMCSV(共創価値)の創出を目指すことを掲げています。これに合わせ、サステナビリティ重要課題を、当社が事業活動を通じて解決していく重要な社会課題である「マテリアリティ」として再定義しました。脱炭素社会に向けた移行期を支えるエネルギーの安定供給責任をしっかり果たしていくこと、人々の豊かな暮らしを実現していく企業として人権に配慮した事業を推進すること、そして、それらの基盤として人材育成・組織づくりを含む確固たる基盤を備えること、この3点を中心にアップデートをしています。
これらマテリアリティに立脚した取り組みのうち、代表的なものとして、(1)「脱炭素社会への貢献」、(2)「地域課題の解決とコミュニティとの共生」、(3)「多様な人材が未来を創る活気に満ちた組織の実現」について詳しくお話しをさせていただきます。
1. 脱炭素社会への貢献(関連する資本:環境・自然資本)
当社は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要なマテリアリティとして「脱炭素社会への貢献」を掲げています。昨年10月に策定した「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」において、パリ協定に整合するGHG(温室効果ガス)排出量の中長期の削減目標(2030 年度半減(2020年度比)・2050 年ネットゼロ)を目指すことにしました。また、中経2024においても、エネルギー需要の充足という使命を果たしながら、SDGsやパリ協定で示された国際的な目標達成に向けた諸施策を打ち出しました。MC ClimateTaxonomyというコンセプトの下で当社の各事業を気候変動の移行リスク・機会に応じて分類し、その分類に応じて「1.5℃シナリオ分析」「トランスフォーム・ディスカッション」「GHG削減目標を踏まえた投資計画」「新規投資の脱炭素採算評価」という4つのメカニズムを適用します。これらのメカニズムの推進により、当社事業のポートフォリオの脱炭素化と強靭化を着実に進めるとともに、EX(エネルギー・トランスフォーメーション)をグローバルに進めていくことを通じて、脱炭素社会の実現への貢献を目指していきます。
また、カーボンニュートラル社会実現のためには、自社だけではなくバリューチェーン全体でのGHG削減が必要となるため、産業や消費者・地域の排出量削減ニーズに寄り添い、ソリューション提供を行う脱炭素ソリューションプロバイダーを目指すことに加え、投資家をはじめとしたステークホルダーからの開示要請が高まっている当社のScope3の排出量(当社におけるScope3排出量の大半を占めるカテゴリー11(販売した製品の使用))の算出・開示についても鋭意検討を継続していきます。
2. 地域課題の解決とコミュニティとの共生(関連する資本:社会資本)
当社の事業遂行においてはコミュニティとの関係構築が不可欠であるとの認識の下、「地域課題の解決とコミュニティとの共生」もマテリアリティの1つとして掲げており、多様なステークホルダー、地域・コミュニティとの信頼関係の上で事業を推進していきます。具体的には、事業を通じた雇用創出・地域開発、コミュニティからの資材調達等、地域と共に繁栄を分かち合うことに加え、先住民の権利への配慮を含め地域への負の影響の最小化に努めています。
3. 多様な人材が未来を創る活気に満ちた組織の実現(関連する資本:人的資本)
三菱商事は時代のニーズを先取り・先読みし、個別事業やその上に成り立つ産業の当事者として、真摯に社会課題の解決に挑み、事業活動を通じて社会とともに持続的成長を実現してきました。その成長を支えてきたのは、社会課題の解決に向けた「高い志」、時代を先取りして新たな価値を導出する「構想力」、国や業界を超えて利害関係者を巻き込みスピーディに構想を実現する「実行力」、そして「三綱領」の精神からつながる「倫理観」を持った人材です。このような人材が、多岐にわたる社会、業界、顧客の課題に対して、主体的かつグローバルな視座・視野を通して最適解を構想し、実行することで価値を創出してきました。従って、三菱商事では、人材を価値創出の源泉、すなわち「人的資本」として捉え、これまでも、これからも積極的に投資していきます。
当社が目指すMCSVを創出し続けるためには、多様な背景や価値観を持つ多彩な人材、また、対面する多くの業界・事業会社から得られた多様な経験・能力を持つ多才な人材が有機的につながり、よりイキイキ・ワクワク、活気あふれる人材と組織であり続ける必要があります。そこで今般、マテリアリティの1つに「多様な人材が未来を創る活気に満ちた組織の実現」を定義した上で、人事施策においては、「人材戦略」「エンゲージメント強化」「データ活用」の3本の柱を立てました。
人材戦略
1つの事象が世界中に瞬時に伝播し、影響し合う環境においては、当社も社会課題に即応できる柔軟な組織である必要があります。経営戦略に応じて、全ての人材がこれまで蓄積してきた知見や能力を十分に発揮できるよう、組織を超えてダイナミックに人材をシフトし、登用します。そのためには、これまで以上に産業横断的な取り組みを推進し、社会のニーズに応えていかなければなりません。これまでも営業グループ体制を改編したことで、組織を超えたグループ間の共創案件・アイデアが多く発案されてきており、EX・DX領域においては、より機動性をもって柔軟に人材を登用・活用するべく、全社タスクフォースを組成し、全社レベルの戦略を立案してきました。DXタスクフォースについては取り組みをさらに加速させるべく、さまざまなグループ出身の人材で構成された産業DX部門に再編成し、営業グループへのDX機能の提供およびDX機能を活用した新規事業の開発を目指します。このように社会課題に対する経営戦略に即応できるよう、最適な組織改編、人材の配置を検討・実行していきます。また、事業環境の変化に応じた能力のアップデートも必要です。特に、中期経営戦略2024で打ち出した成長戦略のEX・DX・未来創造に挑戦・実行できるよう、人材や組織の事業環境変化への対応力強化に向けたリスキリングに取り組みます。
エンゲージメント強化
あらゆる人材が安心・安全な環境で働き、成長・価値創出していくためには、社員がエンゲージメント高く取り組めることが何より重要です。
Diversity、Equity & Inclusion、Well-beingの促進や仕組みづくりを進めるとともに、多様化している個の就業観を尊重し、キャリア自律を促すタレントマネジメントの仕組みを拡充することで、一人ひとりがより責任をもって社会課題に取り組める環境の実現を図ります。
データ活用
人事施策・人材・組織に関するデータを収集・分析・観測し、効果を測定・評価していきます。また、そうしたデータ・情報の開示を充実させることで、社内外のステークホルダーに対するコミットメントを示すと同時に、各種人事施策をより効果高く推し進めていきます。
時代の変化に早期に適応・リードしていきながらも、「高い志」や、「構想力」「実行力」「倫理観」が求められることはこれからも変わりません。組織全体でMCSV創出の原動力となる多彩・多才な人材を育成し、また価値観を共有し合い、つながりながら切磋琢磨し成長できる機会・職場の実現に取り組むことで、継続的に人的資本の価値を最大化していきます。
最後に
このように、マテリアリティをMC Shared Valueの創出に向けた指針とし、事業戦略や取組方針に織り込みながら、社員一人ひとりが持ち場で履践することを通じ、企業価値の中長期的な維持・向上を実現していきます。
Message
入社以来、エネルギー関連事業に約20年、環境関連事業に約10年身を置き、「与えられた場所で、目の前の仕事に真摯に向き合う」姿勢で、業務に取り組んできました。2019年からは、電力ソリューショングループCEOオフィス室長として、電力事業の変革期のなか再生可能エネルギーとデジタルを基軸とした電力システム変革を目の当たりにし、Eneco社経営に関わることを通じ、欧州を起点とする脱炭素の潮流に直接触れることを通じて、サステナビリティへの取り組みが事業に対していかに大きな影響を与えるのか、身をもって実感しました。また、2020年には、より良い組織風土醸成に向けて、部門・グループの垣根、世代を超えたメンバーと会社の目指すべき姿について議論を重ねました。この経験は、多様な役職員が自由闊達な議論を通じて、つながりながら、イキイキ・ワクワク働ける環境を整備していきたいという強い想いにつながっています。
本年よりCAOに就任しましたが、思い返せば上記のような数々の経験から、財務諸表に直接的には表れない非財務に関する取り組みの重要性を認識できたと考えています。この取り組みを強化し、ステークホルダーとの真摯な対話を通じて中長期的な企業価値向上につなげることが私のミッションだと思っています。

