統合報告書2022PDF一覧
目次
-
【イントロダクション】 (PDF:3.3MB)
目次/編集方針/企業理念/社長メッセージ (PDF:1.9MB)/中期経営戦略2024/特集 未来創造(新産業創出/地域創生)/中期経営戦略2021振り返り
-
【価値創造ストーリー】 (PDF:4.1MB)
価値創造の軌跡/価値創造のプロセス/6つの資本/Focus 人的資本 - 価値創出の源泉/マテリアリティ/Focus 気候変動 - EX戦略の前提となるマテリアリティ/CAOメッセージ/CFOメッセージ
-
【営業グループの価値創造】 (PDF:3.4MB)
営業グループ At a Glance/ビジネスモデル ✕ 事業
-
【サステナブルな価値創造を支える取り組み・体制】 (PDF:3.7MB)
サステナビリティ推進体制/リスクマネジメント/コーポレート・ガバナンス
-
【データセクション】 (PDF:2.6MB)
取締役・監査役/執行役員/株主情報/組織体制/グローバルネットワーク(国・地域)/13カ国におけるリスクマネー残高状況/財務ハイライト/主要な関係会社等の持分損益/ESG情報/会社情報



社長メッセージ
総合力を発揮し、「社会や産業の課題」を
ステークホルダーの皆さまと共に解決しながら、
当社ならではの共創価値を創出していきます。
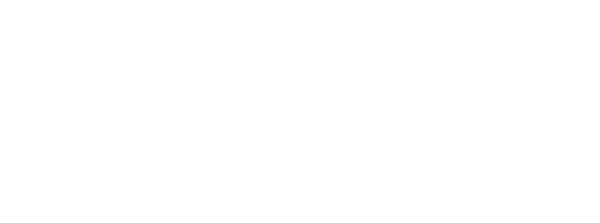
「三菱商事の価値創造」
2022年4月に社長に就任しました中西勝也です。
三菱商事は三綱領の理念の下、時代のニーズを捉え課題を克服するとともに、新たな事業を継続的に創り上げることで、経済発展や人々の生活の向上に取り組んできた歴史があります。そして環境変化に的確に対応し各産業や地域にビジネスを通して深く関わり、長年にわたり蓄積されてきた産業知見やインテリジェンス、そして総合力をはじめとした当社の強みが、さらなる価値創造の源泉となっています。
外部環境については、ここ数年の米中対立により、国家間のイデオロギーの対立と経済活動がますます切り離せなくなっている中、ロシア・ウクライナ情勢に端を発し、世界情勢にはさまざまな混乱が生じています。米・露・中の対立は長期化し、国際社会の多軸化・分断化が進行するなど、地政学リスクの高まりに伴い、政治的な対立が経済活動にも波及し、世界経済は引き続き不確実性を伴って激しく変化していくとみています。さらには世界中を未曽有の混乱に陥れたコロナ禍がもたらしたものの1つとして、将来いつか来ると考えていたモノ・コトの変化の「加速」が挙げられます。技術・イノベーションの進歩により、今後、分野や業界を超えた「競合」や「融合」が非連続的に発生していくことが想定されます。また、グローバルサプライチェーンの再構築や、エネルギー・食料など資源の需給逼迫への懸念、それらに伴うインフレやエネルギー安全保障など、当社を取り巻く環境も大きく変わろうとしています。
このような大きな環境変化がみられる状況下、当社としても、これまで以上に先見性を持ち、変化や不確実性に対応していく必要性を強く感じています。
当社がこれまで培ってきた「産業知見・インサイト」、「グローバルインテリジェンス」、「事業ポートフォリオ変革力」、「財務健全性」、「多彩・多才な人材」、そしてこれらが有機的に「つながる」ことで発揮される「総合力」を最大限駆使し、各事業の総和(Σ)以上の価値を生み出していくことを目指し、本年5月に「中期経営戦略2024 MC Shared Value(共創価値)の創出」を発表しました。事業環境の見通しが不透明な状況下においても、事業を通じた社会課題の解決を通じて、スケールのある共創価値を創出し続けていくとの強い想いを込めたものです。
「中期経営戦略2021」を振り返って
中経2021では、「事業経営モデルによる成長の実現」を掲げ、経営力の高い人材を継続的に輩出することを目的として、大規模な組織改編を断行し、併せて約20年ぶりに人事制度改革も行いました。これにより経営人材の育成と登用の推進、評価・報酬制度の見直しによるメリハリのある処遇の実現や、分野を超えた人材配置・全社タスクフォースの設置などの全社横断的な取り組みが進みました。
事業ポートフォリオについては、Eneco社の買収やHERE社への出資、ジャカルタ郊外のスマートシティ開発をはじめEnergy Transformation (EX)・Digital Transformation (DX) に関連した「川下」領域や「サービス」分野、「エネルギー・電力」分野の取り組みが進捗しました。また、ペルー・ケジャベコ銅プロジェクト開発、豪・ボーキサイト鉱山オールクンの権益取得など、電化の進展に関連した「川上」領域の強化も進みました。
成長メカニズムとして掲げた循環型成長モデルについては、低成長・低効率の資産についての見極めに加えて、MC-UBSR社に代表される、よりふさわしいオーナーへの事業譲渡なども含め、事業の入れ替えが相応に進みました。加えて、コロナ禍を踏まえた足元強化への対応として赤字会社の黒字化や入れ替え方針に対する管理の強化を進めました。
また、昨年10月には「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」を策定しました。2030年度のGHG排出量半減、2050年のネットゼロ宣言に加え、2030年度までのEX関連への2兆円規模の投資、「EX・DXの一体推進による地域創生を通じた未来創造」を全社共通の事業推進テーマとして打ち出しました。Eneco社の知見も活用した国内洋上風力3案件を落札し、MC Digital、Industry Oneを核とした産業DXの推進など、順調に取り組みを進めています。
定量的には、2020年度にはコロナ禍の影響を受け大幅減益となった一方、前中経最終年度であった2021年度の連結純利益は、資源価格の堅調な推移に加えコロナ禍からの需要回復を各事業で着実に利益につなげ、過去最高の9,375億円となり、ROEは15%に達しました。今後も環境変化が激しい状況が続くことが想定される中で、2021年度は市況の追い風の影響が相応にあったことも踏まえ、資源価格の変動にかかわらず、着実に収益レベルを向上させる必要があると認識しています。
また、依然として投資利回りの低い事業が残っていることは継続課題として認識しています。循環型成長に終わりはなく、常に先々の環境を見通し、自ら事業ポートフォリオを変革させていく意識を持ち続けることが肝要であると考えています。
「中期経営戦略2024 MC Shared Value(共創価値)の創出」
中期経営戦略 2024で打ち出した「MC Shared Value」とは、「三菱商事グループの総合力強化による社会課題の解決を通じて、継続的に生み出されるスケールのある共創価値」です。脱炭素社会、持続可能な社会と暮らし、イノベーション、地域コミュニティとの共生など、さまざまな社会課題がある中で、当社ならではの強みを活かし、その課題解決を通じて「MC Shared Value」を創出していきます。


定量目標・株主還元
定量目標としては、2022年度の連結純利益を8,500億円、2024年度を8,000億円とする計画としました。市況変動の影響が大きい中で、2024年度は一定程度保守的な資源価格前提の下で見通しを策定しました。2024年度と同じ資源価格前提を2022年度に当てはめた場合の利益見通しは6,500億円となります。この資源の価格要因を除いた6,500億円から2024年度の8,000億円への利益成長は、既存案件の成長や循環型成長モデルに基づく資産入れ替え、新規投資などにより達成していく見込みです。市況変動による価格要因を除いた利益の着実な成長により、二桁水準のROEの維持・向上につなげていきます。
株主還元については、財務健全性、配当の安定成長、還元に対する市場期待の3つのバランスをとりつつ、持続的な利益成長に応じて増配を行う累進配当制を維持し、30~40%程度の総還元性向を目処とした還元政策を進めていきます。
EX投資の加速
中経3年間の投資は、3兆円規模を想定しています。収益基盤の維持・拡大を図りつつ、そこで創出したキャッシュ・フローをEX関連やDX関連・成長投資関連にも配分していきます。特にEX関連投資については、昨年10月のロードマップにて策定した「2030年度までに2兆円規模」を加速させ、2024年度までに1.2兆円規模の投資を計画しています。
投資の分野としては、欧州と日本で先進的に取り組んでいる洋上風力をはじめとした再エネや、加速度的に進展する電化社会を支える銅などのベースメタル・レアメタル、さらにはトランジションエネルギーである天然ガスや水素などの次世代エネルギーとなります。
当社は再エネへの投資を拡大していきますが、脱炭素という社会課題に対する取り組みの入り口が再エネであり、当社の総合力をもってこれを起点にカーボンニュートラル新産業の創出につなげていくことで低・脱炭素化を推進し、社会課題の解決に挑戦していきます。
トランジションエネルギーとして位置づける天然ガスについては、安定供給の社会的責任の観点からも引き続き重点的に取り組む事業であると位置づけています。日本のエネルギー安全保障をはじめ全体的なバランスを見ながら取り組んでいきます。
EXの代表例であるエネルギーや資源分野の事業開発には相当な時間を要します。将来のニーズを取り込むには、5年、10年先の未来を見据え、先手を打つ必要があります。
だからこそ、まずはEX分野に加速度的かつ重点的に投資を行いたいと考えています。当社は事業活動を通じて、さまざまな産業と接点を持っていることに加え、資源・エネルギーの安定供給とその供給体制づくりに当事者として長年携わってきました。幅広い事業を通じて蓄積したノウハウやネットワークを活かし、信頼できるパートナーと共に安定供給と脱炭素社会への移行の両立に貢献したいと考えています。また、このようにしてEX投資を進めることにより、事業ポートフォリオにおけるEX投資の割合を、現時点の3割から、2024年度末には4割程度、将来的には5割程度まで引き上げていきます。
当社ならではの総合力最大化に向けた施策
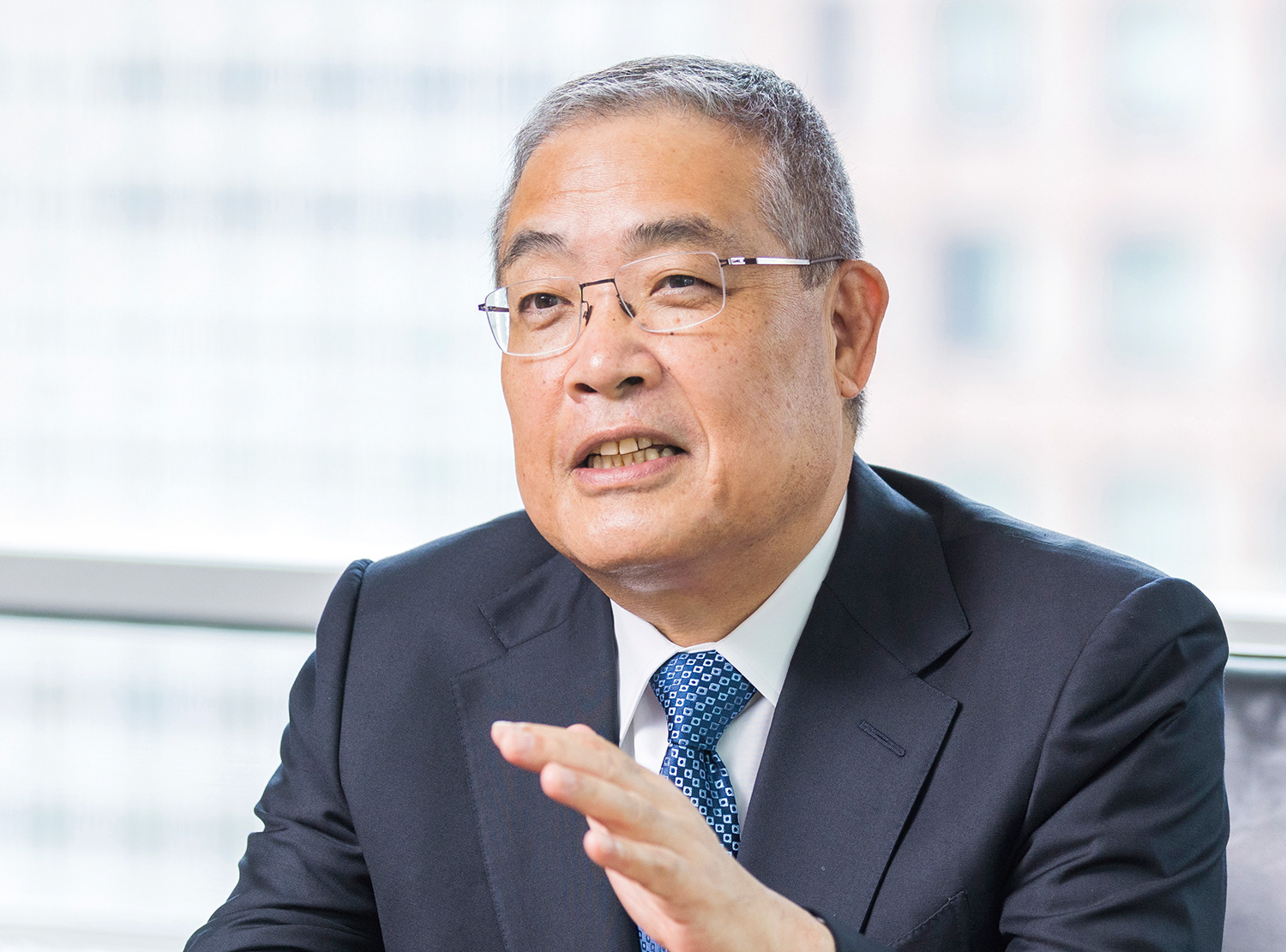
「MC Shared Valueの創出」に向けて、中経では、成長戦略、経営管理、推進メカニズム、人事施策、サステナビリティ施策の5つの施策を導入しました。
まず、成長戦略としては「EX戦略」、「DX戦略」、そしてEX・DXの一体推進による地域創生を通じた「未来創造」を掲げました。「未来創造」は当社が強みを有する再エネなどの地域エネルギー資源を活用し、カーボンニュートラル新産業の創出や、地域課題の解決を通じた魅力ある街づくりをテーマとした取り組みで、後ほど詳しく説明します。
経営管理については、循環型成長モデルへの取り組みを加速するとともに、営業グループの自律的な経営を強化すべく、入れ替え計画・グループROE・管理キャッシュ・フロー(CF)制度による経営管理メカニズムを導入しました。営業グループが利益成長を目指すと同時に、入れ替え計画に基づく低利回り先の入れ替えや、ピークアウトした資産の売却によるキャピタルゲインの獲得を加速していくことで、グループROEの向上を通じて、全社ROEの二桁水準の維持・向上につなげていきます。また、管理CF制度の導入により、創出したキャッシュの一部を全社で留保し、全社横断的な案件などに投資することで、事業ポートフォリオの変革を進めていきます。さらに、「循環型成長レビュー」によるモニタリングを定期的に実施し、これらの実効性を高めていきます。
推進メカニズムについては、DX戦略の推進を担う産業DX部門、および外部環境変化をタイムリーに事業戦略に反映すべくグローバルインテリジェンス(GI)委員会を新設しました。各営業グループが推進力を高める、いわゆる「タテ」の強靭化と、業界の垣根を越えた「ヨコ」の連携により、総合力の最大化も進めていきます。産業横断的な全社戦略は、GI委員会でのインプットも踏まえつつ、MC Shared Value会議を通じて推進していきます。
人事施策については、多彩・多才な人材がイキイキ・ワクワクしながら仕事に取り組み、やりがいと誇りを持って主体的に責任を果たす企業風土をつくり上げることで、社員全員の活躍と成長を後押ししていきたいと考えています。人材戦略、エンゲージメント強化、そしてデータ活用の三本の柱で施策を推進していきます。
サステナビリティ施策については、社会、環境課題の変化に応じてマテリアリティをアップデートしました。マテリアリティを含む社会課題に対して、事業活動を通じて解決していくことで、共創価値を生み出していきます。
未来創造・地域創生
成長に向けた具体的な打ち手として、EX・DXの一体推進による地域創生を通じた「未来創造」を掲げています。
まず、成長戦略に「未来創造」を掲げた想いをお話ししたいと思います。産業競争力を維持しながら低・脱炭素化に対応することは、全産業が共通して直面している課題です。一方、日本に目を転じれば、GDPはここ30年ほとんど伸びておらず、エネルギー・食料の自給率は低く、多くを海外に依存するなど、安全保障上の問題が浮き彫りになってきています。喫緊かつ根源的なこの課題に、真正面から向き合っていく必要があると強く感じています。
今回、この未来創造に記載した内容は、当社が強みを有する再エネを起点とした構想です。再エネは地域に存在するエネルギー源そのものです。この地域エネルギー源で自給自足率を上げ、そして、新たなカーボンニュートラル(CN)産業の創出と、地場産業の強靭化 、人口減少による就労者確保の難しさなどの地域社会の課題を解決する取り組み、すなわち、「地域創生」をテーマとして、未来創造に取り組んでいきます。

図の左側は、再エネ起点のグリーン電気・グリーン水素についてです。電気として使うのみならず、水素を原料とした製造事業、供給サイドを地域の新たな産業として立ち上げていくことを目指します。産業との接地面を多く有する当社の強みを活かし、ニーズの掘り起こしからソリューションにつなげていくものです。
図の右側は、地域社会についてです。まず、再エネは地域インフラ開発そのものであり、プロジェクトに携わる人材育成や関連産業の誘致など、地域での雇用創出が期待できます。これは、「人が集うコミュニティ」・「魅力ある街に」というテーマで、そこに暮らす住民の方々のQuality of Life向上に資する取り組みです。 DXにより地域のさまざまなデータをつなげ、新たな生活関連サービス ・事業開発による生活者の利便性向上にも取り組みます。
昨年、開発事業者に内定した洋上風力発電事業では、地域の方々から三菱商事グループへの期待をつづった手紙を頂きました。10年20年という時間軸で地域とつながり、当社としていかに期待に応えていけるのか、地域と一緒にどのような手を打っていけるか。地域の期待に応えたいという想いとともに、その責任を強く感じています。この構想は当社単独でできるものではありません。時間軸も長く、壮大な計画です。行政・自治体・地元企業との連携、また、同じビジョンに賛同して頂けるパートナーと共に、地域創生を進めていきます。さまざまな社会課題の解決を通じ、産業全体の発展と地域色豊かな未来社会の実現に貢献していきたいと考えています。
「最後に」
先を見通すことが難しい不確実性の高い今のような時代こそ、当社の多様性・総合力を最大限に活かすことで、優位性を高めることができると考えています。
また、インターネットやデジタルの普及により瞬時に世界の情報が入ってくる時代になっているものの、やはりビジネスの現場からの鮮度の高い情報が大切であり、それを連結ベースでタイムリーに捉え、真贋を見極める力を発揮し、選別して経営に活かしていくことが重要です。
産業知見とグローバルインテリジェンスにより環境変化の半歩先に対応し、多様な要素を各々つなげることで、当社ならではの共創価値を創出していきます。
社会課題が複雑化・多様化する中で、投資家・株主をはじめとする多様なステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを大切にし、経済価値・社会価値・環境価値の同時実現を進めていくことで、皆さまの期待に応えていきます。
私の最初の駐在は1990年代初頭のコロンビアでした。当時コロンビアは政治情勢が安定せず、当社にとってビジネスの機会が限られる環境に悩みましたが、注文が取れなくても情報は取ろう、と情報収集に奔走しました。今振り返ると、私のように世界各国に散らばる社員一人ひとりが情熱と意思をもって収集するあらゆる情報が「つながる」ことで、三菱商事グループの総合力を支えているということを、最初に肌身に感じたのがこの国での駐在でした。
これまで仕事と向き合う中で、私がずっと大切にしてきたのは、結果にこだわるということです。もちろん、すべてうまくいくことはあり得ません。大切なのは、成功確度が低くても諦めないことです。Lessons Learned̶結果にこだわらないと、失敗が失敗のままで終わってしまう。成功するためには、失敗を糧に形を変えてでも挑戦し続けることです。そうしてやり遂げた一つの結果が新たな自信になり、諦めない心につながっていくのだと考えています。

